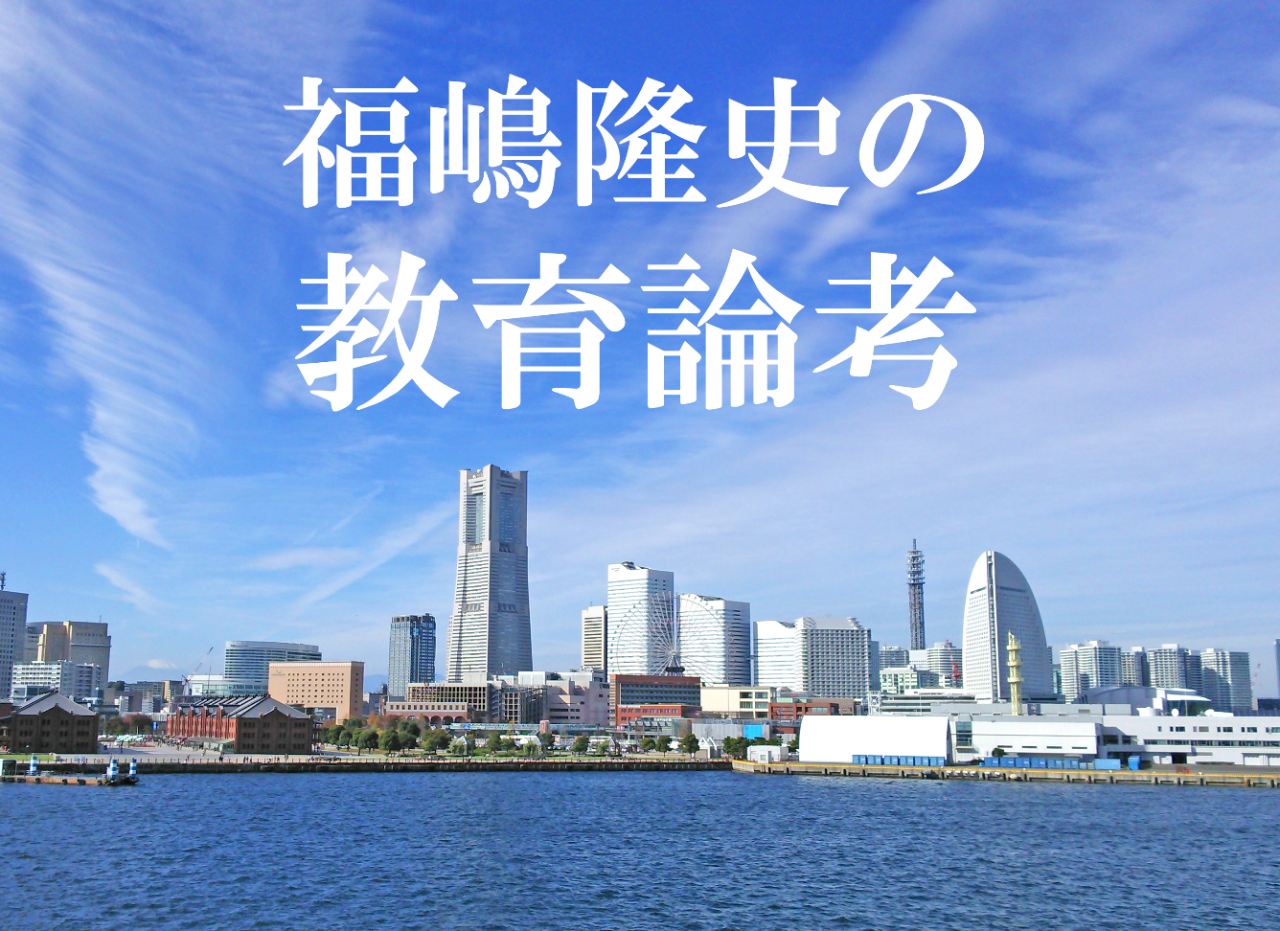
2016年12月6日、「OECD生徒の学習到達度調査」(PISA2015)の結果が公表されました。なんと、翌7日の読売新聞では、一面トップでこれを報じています。しかし、記者の捉え方も識者の意見も、どうも的はずれです。「読書量減少が原因」だとか、思いつきのこじつけ解説ばかり。具体性のある議論をしていないから、そうなるのです。
その読売新聞記事の中でも触れられていた報道、“教科書を読めていない中高生”に関して、私は以前、綿密な分析を行いました。その内容は、2016年5月に有料メルマガ号外の形で公開しました。有料メルマガでは、号外及び通常号を含む5月号のバックナンバーを810円(税込)で購入できますが、このたび、PISA読解力低下の報を受け、急遽、号外のみを単体のmine記事で販売することにしました。
具体的な検証とはどういうものなのか。それをじっくりと確かめていただきたいと思います。
現場教師がこうした具体的な検証を行い、それを授業へと還元していくこと抜きにして、読解力向上など、あり得ないのです。
以下、号外記事転載です。
◇信じがたいほどの正解率の低さ
2016/5/25(水)の読売新聞朝刊「解説」ページ(12版・13面)に、「人工知能に負けるな」と題された記事がありました。
そこでは、東大合格を目指す人工知能「東ロボくん」の生みの親である国立情報学研究所の新井紀子教授による興味深い調査の結果が紹介されていました。
記事中で「意味を理解しているはずの人間が、意味を理解していない人工知能に負けるのは変だ思いませんか」と語る新井教授。
「そこで今年2月、首都圏や近郊の教育委員会に協力してもらい、教科書の文章から作った問題で読解力を調べてみました。対象は中学・高校8校の約1000人です。サンプル数が少ないので確定的なことは言えませんが、教科書をきちんと読めない生徒が少なからずいる可能性があることがわかったんです」と続けます。
この記事のサブタイトルは、「教科書読み解けぬ中高生」「職種変化 対応に不安」でした。後者は、職種を機械が代替していく未来への危惧についてです。この点については、私が直接関知することでもありません。
問題は、前者です。
果たして、本当に「読み解けぬ」のか。
そこに掲載されていた問題例を見て、これはぜひともわが塾の生徒にも試してみなければ、と思いました。何しろ、調査結果に記された正解率があまりに低いのです。
これは、私が日々主張する国語教育の悪質さの証左ではないか。そう思いました。一方で、技術を与えている当塾の生徒なら少しは良い結果が出るはずだ、とも考えました。そこで、授業を割いてこれ(2問)を実施。その結果がまとまりましたので、分析とともに、ここでお知らせする次第です。
問題は、次の通り。
【問1】アミラーゼという酵素はグルコースがつながってできたデンプンを分解するが、同じグルコースからできていても、形が違うセルロースは分解できない。
★ セルロースは( )と形が違う。
A デンプン B アミラーゼ C グルコース D 酵素
【問2】仏教は東南アジア、東アジアに、キリスト教はヨーロッパ、南北アメリカ、オセアニアに、イスラム教は北アフリカ、西アジア、中央アジア、東南アジアにおもに広がっている。
★ オセアニアに広がっているのは( )である。
A ヒンドゥー教 B キリスト教 C イスラム教 D 仏教
※出典:読売新聞2016年5月25日朝刊|問1:東京書籍・高校生物基礎教科書『新編・生物基礎』|問2:東京書籍・中学校社会教科書『新しい社会地理』
さて、当塾での結果と、1000名調査の結果とを併記し、以下に記します(1000名調査の結果は、上記新聞記事が出典)。
この「一文読解」をいかにして指導するかについても、細密にご紹介します。
