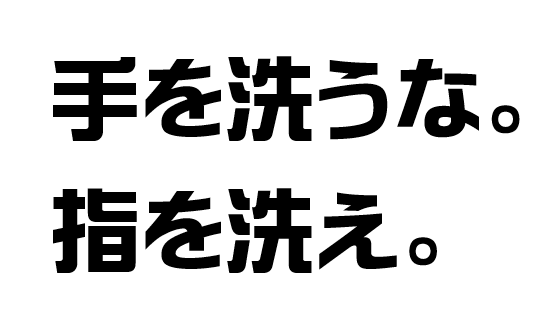
最近私は塾において、子どもたちの手洗いが「しっかり」できているかどうか、その場でチェックしている。
すると、驚くほどに、できていない。
小学生だけでなく高校生でも、まともに手を洗えていない。
「指先まで丁寧に洗いなさい」などと言っても、効果はイマイチ。
困ったもんだと嘆いていたわけだが、今さっき、有用と思われる声かけを思いついたので、メモしておく。
× よく手を洗いなさい。
× 丁寧に手を洗いなさい。
× しっかり手を洗いなさい。
× きちんと手を洗いなさい。
○ 手を洗うな。指を洗え。
これだ。
まず、「指を洗え」というフレーズの具体性。
どんな指示であれ、子どもへの指示は、具体的に、行動に直結するような言葉で行うこと。これが指導の原則なのだ。
そして、「手を洗うな」。
いきなり「手を洗うな」と言われたら、「え、なぜ?」と思う。
そこで、子どもは意識を向けてくれる。
子どもの頭が瞬時に働き出す。
そして、少しだけ間をおいて「指を洗え」と言えば、「ああなるほど」となる。
その納得感が、行動を促す。
念のため書いておくが、「指だけを洗え」という意味ではない。手のひらや手の甲、あるいは手首も含め、全体を洗うべきであるのは言うまでもない。
あくまでも、「部分」に注目させるために思い切って「全体」を意味する言葉を捨てよ、というだけのことだ。
子どもの頭を働かせるという意味では、こういうのもいい。
問い:「手を洗った直後、すぐ手をよごす方法がある。それは何か?」
ここで少しだけ考えさせる。で、答え。
答え:「蛇口(やレバー)を素手で触ること」
ペーパータオルで手をふかせるのが、ベスト。
そして、手をふいたペーパーを使って、間接的に蛇口やレバーに触れること。
それが、せっかく洗った手をよごさないようにするための手段になる。
前々から思っていることだが、子どもたちは、ハンカチをポケットにしまっている。手をふいた直後のぬれたハンカチも、平気でポケットにしまいこむ。雑菌を繁殖させるつもりなのだろうか。
ハンカチを使うなとは言わないが、乾かせる環境であれば、どこかにつるして乾かすような工夫をしたいものだ。
ともあれ、「手を洗うな。指を洗え」。
ぜひ、今すぐ子どもたちに伝えてみていただきたい。
