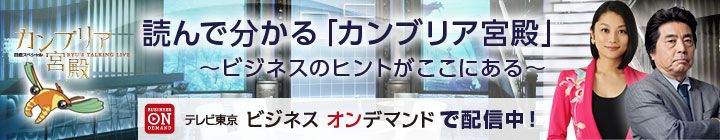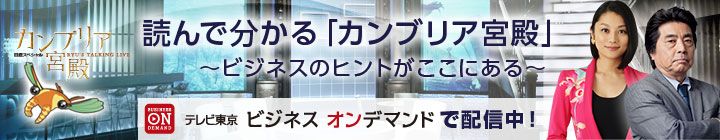行列のできる博多の人気店のヒミツ
日本で最も売れている明太子メーカー、ふくやの太宰府店。地元はもちろん、ここの味を求めて、全国から観光客もやってくる。
一番人気は「味の明太子」、360グラムで3240円。「激辛明太子」2160円。付属の特性ダレで辛さを増すことができる。さらに数の子やイカなどと和えた惣菜風の一品「あえもの明太子」756円など、およそ20種類もの明太子商品を扱っている。
店のもう1つの人気が店の奥にあるイートインスペース。「明太子お茶漬けセット」が食べられる。大分県産のヒトメボレのご飯に、特製の「ふぐダシ」をかけて。ご飯とダシはお替り自由で756円。
「普段の売上は30~40万円。90万円いくことがあります」(大宰府店・佐藤友香)
地元客にも観光客にもふくやの明太子は大人気。売上は全国の明太子メーカートップの149億円に達する。
明太子の原料は塩漬けしたスケトウダラの卵。いわゆるタラコだ。1日に使うタラコの量はおよそ8万本。その全てを人の目と手でチェックし、状態の良いものだけを商品にしている。
明太子の味を決める秘伝のレシピ。ふくやでは3種類の唐辛子を独自の割合で配合しタラコのうま味を引き出している。「タラコ本来のうま味を唐辛子で引き立てるようにブレンドしている」(製造部・橋田集)。この唐辛子をベースに作ったのが秘伝の調味液。これをタラコにタップリかけ、2日間漬け込んで味を熟成させるのだ。

明太子とともの成長したふくやの歴史
九州一の繁華街、福岡・中州にあるふくやの本社。創業68年のふくやは、今や従業員635人を抱える福岡を代表する地元企業だ。
本社に一枚の写真が掲げられている。ふくやの創業者、川原俊夫。実は俊夫こそ、明太子の生みの親なのだ。
俊夫は戦後、韓国の釜山から引き揚げてきて、中州に食料品卸の店を構える。これがふくやの始まり。店の目玉にと俊夫が目を付けたのが、釜山でよく食べていた「タラコのキムチ漬け」。1949年、「明太子」と名付けて売り出したが、まったく売れなかった。
そこで俊夫は10年をかけて、調味液に漬け込む今の明太子を作り上げた。その明太子は評判となり、博多の町に広がっていった。
とはいえ昭和30年代、明太子はまだ地元博多だけで人気の惣菜に過ぎなかった。それがいまや全国で食べられるように。これを実現させたのもやはり俊夫だった。
ふくやの明太子が博多の街に広がり、真似する業者も出始めてきた頃、友人たちは、俊夫に「特許を取ったほうがいい」と助言した。しかし俊夫は「ただの惣菜だから」といって特許をとらなかった。それだけではない。明太子を作りたいという人たちに、惜しげもなく作り方を教えた。
かくして明太子は、博多の名物になっていった。さらに1975年、新幹線で東京・博多間がつながる。出張や観光で福岡を訪れる人たちに、明太子は絶好のお土産として注目を集め、全国に知られるまでになった。
いまや福岡の名産品となった明太子。福岡県内だけでも、150以上の明太子メーカーがあるという。明太子の市場規模は、じつに1300億円。巨大な地場産業となっている。

ふくやはなぜ特許を取らなかったのか
いまなお博多の人たちは、特許をとらなかった俊夫に、感謝の念を抱いている。
福岡の老舗料亭が出している明太子専門店「椎加榮本舗」。いわばライバルだが「私たちも後発組だが、気兼ねなく市場に参入できる土壌を作ってくれた。ありがたい存在、明太子文化の生みの親、という意識はあります」(営業部長の田原義太慶さん)という。
俊夫はなぜ製造特許を取らなかったのか。村上龍の質問に、敏夫の次男で現社長の川原正孝はこう答えている。
「父が作り始めたときはまったく売れず、辛すぎて苦情がきたほどです。それが売れ始めると、自分の店だけで売ればいいのに、他の店にも作り方を教えるので、一緒に作ってきた社員は怒っていました。そうしたら父は『そんなに怒るなら、お前らも作っていい』と、独立させました。ふくやだけの味だったら、合う人と合わない人がいるから、いろいろなメーカーがあっていろいろな人に食べられたほうがいい。『だからいろいろな味があったほうがいい』と言い続けていました」
結果的に、それが明太子のマーケットを広げていった。
「うちは2店舗しかなかったんです。駅にもデパートにも空港にも出していなかった。でも他のメーカーがデパートに出店したり、東京に進出したから明太子が広がっていった。もし製造特許を取ってどこにも作り方を教えていなかったら、業界の売上は今の10分の1もなかったんじゃないでしょうか」

「元祖」の地位にあぐらをかかず、進化を続ける
博多っ子が愛してやまない明太子。主婦たちにはそれぞれ自慢の明太子のアレンジ料理があるようだ。もちろんふくやも明太子の可能性を広げようと、日々開発に励んでいる。開発中の商品を見せてもらった。一見普通の明太子のようだが、実はカレー味。
「ちょっと変わり種の明太子を開発しようという事で、皆さんが好きな、一般受けが良いカレーがいいんじゃないかと」(商品開発課・上野晶子)
こういった試作品を年間20種類以上作っているという。そんな開発で生まれたヒット作が独自の味付けをしたチューブ入りの明太子だ。
たとえばオリーブバジル風味。じつはこの中には、明太子の粒と同じ大きさの、バジルエキス入りのカプセルが入っている。カプセルは体温で溶けるため、食べた瞬間、味と風味が口に広がる。
明太子を調味料感覚で、気軽に使ってもらおうという、アイデア商品。ほかにも、ユズや、ゴマ油の風味など、全部で11種類。3年前の発売以来、累計60万本を売り上げる大ヒットとなった。
元祖や老舗という地位にアグラをかかず、進化を続ける。それがふくやの原動力になっている。

ふくやが地元で愛されるもうひとつの理由
社員が見せてくれた「ふくや手帳」。このふくや手帳は川原をはじめ社員全員が持っている。そこには経営理念が、「強い会社、良い会社」と書かれている。
「強い会社というのは、やはり利益を出すこと。良い会社っていうのは、その利益から、地域のためにやるとか、夢をもっていろいろなことをやるとか」(川原)
すなわち、ふくやの信用力は、得た利益を地域貢献に使う。つまり地域とともに生きることで培われてきたのだ。それを実践する部署が「網の目コミュニケーション室」だ。
「いろいろな地域のイベント、スポーツ大会に後援したり、人を派遣したりとかを実行している部署になります」(室長・宗寿彦)
年間に来る後援の要望は200件以上。博多最大の祭り、山笠はもちろん、少年野球大会の協賛、同窓会誌への協力といった小さなものまで。もちろん、熊本地震の支援も行っている。
こうした寄付やボランティアに使った金額は、去年でおよそ1億5000万円。7億円の利益のうち実に20%を地域のために使っている。
お金を出すだけではない。社員一人ひとりも、地域貢献に参加できる仕組みがある。
お客様サービス室で働く西野健太には、もう一つの顔がある。夕方6時、とある体育館を覗いてみると、小学生の柔道の稽古が行われていた。そこでコーチを務めているのが西野だ。西野は柔道3段の猛者。17年前から、週に3日、地元のスポーツ少年団で柔道のコーチを務めている。練習の日は会社から残業を免除されているという。
4月は入学のシーズン。ある小学校で祝辞を述べているPTA会長は、配送センターに勤める製造物流部・高良咲應だ。PTAの活動は平日の昼になることが多い。ふくやでは、PTAの活動で勤務を抜けても、出勤扱いになるという。
仕事を抜けられるだけではない。給与明細を見せてもらうと5000円の地域ボランティア手当が支給されていた。少年サッカーチームの監督・5000円、保育園父母会会長・3000円、青少年指導委員・3000円……ふくやは社員にさまざまなボランティア手当を支給して、地域活動をバックアップしている。
「地域貢献というよりは、地域の方が、ここにふくやがあって良かった、工場がここにあって良かったと思っていただける会社になりたい」(川原)
しっかり利益をあげて、それを地元のために使う。それがふくやの目指す「良い会社」だ。

「利益を追求する」感動経営
創業者・川原俊夫には、もう一つこだわりがあった。それは「税金を一番多く払うこと」。事実、1979年には、管轄する税務署管内で高額納税者の1位になっている。
当時、ふくやはまだ個人商店。銀行の支店長をしていた川原の兄が「そろそろ法人化したほうがいい。税金も安くなりますよ」と進言したところ、俊夫は「道路はなんでできている? 橋はなんでできている? 全部税金じゃないか。なぜ多く払っていけないんだ」と怒り出した。川原は父・俊夫の真意をこう語る。
「父には“地域のために”という思いがあったが、一番大切にしていたのは『利益を出して税金を納め、雇用を守ること』でした。だから『絶対に利益を出す』『赤字を出さない』と言い続けた」
村上龍はそんな俊夫の考え方を、戦争が終わり、生き残って戦地から故郷に帰ってきた彼の人生から導き出されたのではないかと感じていた。川原は「まさにそうだ」と言う。
「それまでの父の人生は自分のためのものだったけれど、船で福岡に帰ってきたときに、『これからは人の役に立たなければ申し訳ない』と思ったのでしょう。福岡の電力会社に就職が決まっていたのに、サラリーマンだとそのための資金も時間も足りないということで、商売人になろうと思った。そして利益を地域のために使おうという思いで、ふくやが生まれたんです」
明太子だけじゃない!意外なふくやの新戦略
いま、ふくやは、食で九州を盛り上げる取り組みを始めている。その舞台が、ふくやが運営するスーパー「たべごろ百旬館」。
並んでいるものがちょっと変わっている。マジャクというシャコの親戚。有明海で獲れる、知る人ぞ知る珍味。イソギンチャクは、有明海の周辺では、みそ汁に入れたりするそうだ。他にも超長いナスなど、九州のちょっと変わった食材を集めている。
実はこの店の主な客は、飲食店関係者。ふくやは九州の知られざる食材を、プロの料理人たちに使ってもらうことで広めようとしているのだ。
ふくやは産地や生産者も育てようとしている。それを担うバイヤーの一人、食材営業部の濱地武範。訪ねたのは、朝倉市で新たな名産品を作ろうと頑張っている生産者だ。
その食材はビニールハウスの中で育てられていた。中には巨大な水槽が。育てられていたのはウナギ。ここでは発電にも使われる地熱を使い、養殖場の水を28度に温めている。こうすることで、通常出荷まで1年近くかかるところを、4ヶ月ほど短縮できるという。
おいしいウナギに育てるため、さらなる工夫が。それがこだわりのエサ。出荷前の一定期間だけ、シャコの殻と粉末状にした白身魚の身を混ぜたエサを使っている。普段使っているイワシの粉のエサでは、ウナギに、どうしても魚臭さが残ってしまう。そこで、出荷前にエサを切り替え、臭みのないウナギを育てているという。
かくれた食材を発掘し、生産者も育てて九州全体を盛り上げる。これもふくや流の地域貢献だ。
一方、2年前にオープンした、ふくやが運営する店「海食べのすすめ」。この店のコンセプトは、地元産ではなく、全国の旨いものを提供することだ。
「以前は博多の美味しいものを全国に出そうとしていた。今度は博多の人たちに全国の美味しいものを食べていただこうという思いで作りました」(川原)
食を通じて地元福岡に貢献する。ふくやの地域に対する思いは、創業から今に至るまで、ずっと変わらない。

~村上龍の編集後記~
相撲好きだった祖父は、九州場所で福岡に行くと、必ず「味の明太子」を買った。当時の佐世保の明太子と違って、色も、香りも、味も、上品だった。わたしは子ども心に、「きっとお金持ちが作っているんだろう」と思っていた。
そうではなかった。「ふくや」は、戦争引き上げの創業者が、ひたすらおいしいものを提供し、世に貢献するために創業した。製造技術をオープンにすることで市場が拡大するというビジネスの王道を貫いた。
その経営理念は脈々と受け継がれ、明太子は、珍味ではなく、庶民の総菜として、広く、深く、今も親しまれている。
<出演者略歴>
川原正孝(かわはら・まさたか)1950年福岡生まれ。父はふくや創業者の川原俊夫。1973年、甲南大学経営学部卒業後、福岡相互銀行入行。1979年ふくや入社。1997年社長就任。