
満開の梅に茶懐石~和の魅力満載の里山
琵琶湖を望む滋賀県大津市。湖のほとりから30キロほど入った山あいに人気の施設があるという。
3月、そこには見渡す限り満開の梅が。この見事な光景を一目見ようと、家族連れやカップルが殺到していた。この日だけで2000人の観光客が押し寄せた。
梅の木はおよそ1000本。京都に古くから続く「城州白梅」という品種で、花だけでなく、夏には大粒の実を付けるという。
ここは「寿長生(すない)の郷」。6万3千坪の敷地に日本の昔ながらの里山が広がる。
敷地の一角で相撲が始まった。こちらでは和太鼓の演奏。まるで懐かしい村祭りのようだ。お食事処「山寿亭」では旬の食材をふんだんに使った懐石料理が味わえる。食事の締めは別席に移って裏千家のお点前を体験。「寿長生懐石」(お茶席付き)は6480円。そして子供には生け花体験も。ここはまさに「和のテーマパーク」だ。
そんな「寿長生の郷」にひときわ客の集まる場所がある。お目当ては和菓子。ここの一番人気の商品は「あも」(1188円)というお菓子だ。一見、羊羹のようだが、餅に水飴を加えた求肥(ぎゅうひ)を大粒の小豆餡で包んである。トロリとした食感が人気の秘密だ。
ここは叶匠壽庵(かのう・しょうじゅあん)という和菓子店。そして「寿長生の郷」は叶匠壽庵が持つ施設なのだ。
叶匠壽庵といえば主なデパ地下には必ず入っている。全国におよそ80店舗を展開、絶大な人気と信頼を得ている和菓子の店だ。
叶匠壽庵の本社は「寿長生の郷」にある。趣のある「長屋門」をくぐるとまるで和風旅館のような光景が広がる。その一角にひなびた建物が。中をのぞいてみると、ひとりの職人が菓子作りに没頭していた。叶匠壽庵三代目社長、芝田冬樹だった。
職人だった芝田は先代社長の娘婿。5年前、三代目社長に就任した。三代目の芝田は初代の教えを守り、里山の自然に根差した菓子作りを心掛けている。春には菓子で花見弁当を表現。秋には裏ごしした栗を皮で包んでみる。この「寿長生の郷」の自然と、そこに息づく日本文化が、初代と二代目から受け継いだ最大の財産だと、芝田は考えている。
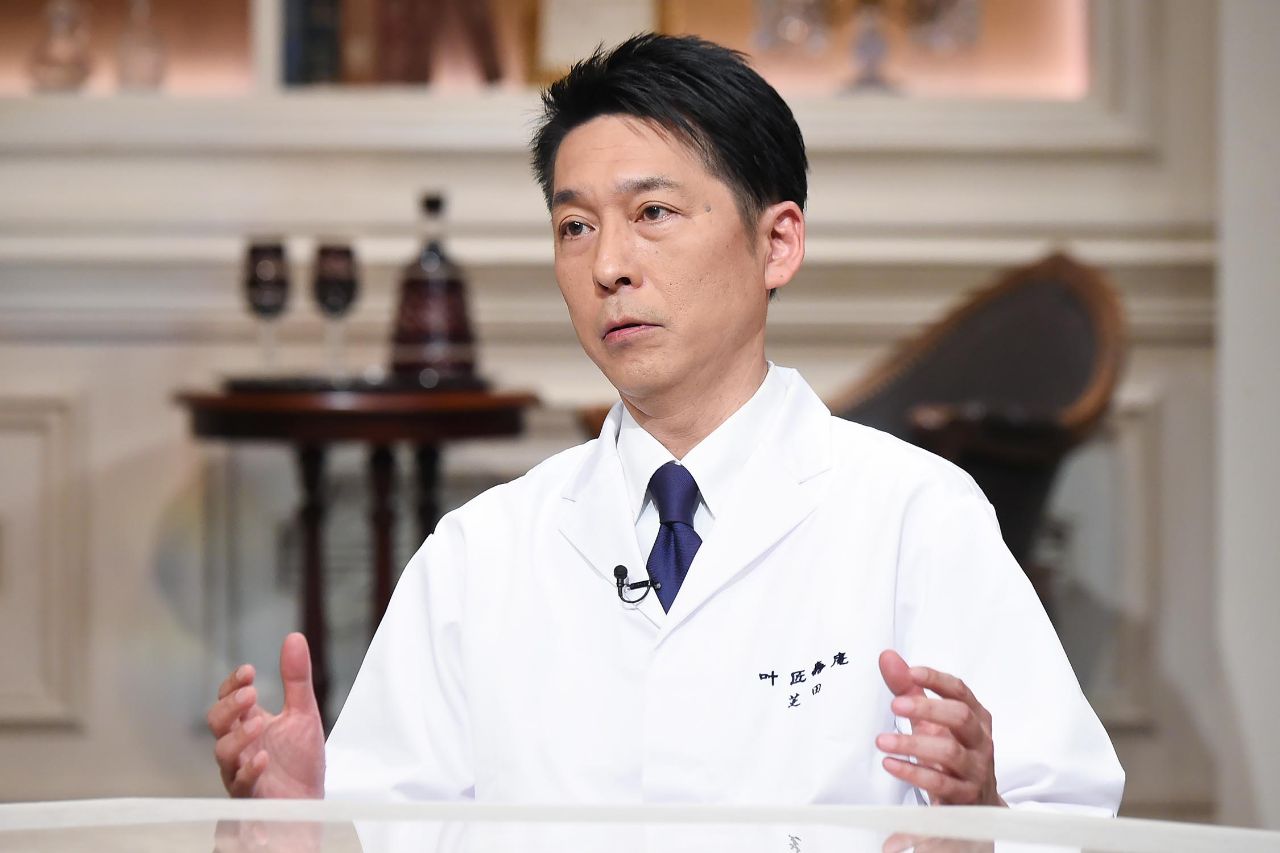
京都の老舗を脅かす~“和菓子のソニー”が大躍進
叶匠壽庵は1958年、和菓子の本流、京都から少し外れた滋賀県大津市の小さな店から始まった。創業者の芝田清次は、京都に負けない、これまでにない和菓子を作ろうと考えた。
当時、羊羹や饅頭が一般的だった和菓子に、清次は革命を起こす。ヒントは京都の舞子たちが「あんも」と呼んでいた「あんころ餅」。そこから生まれたのが、あの「あも」だ。これまでにない食感で、叶匠壽庵を代表するお菓子となった。
清次の革命がもう一つ。紅色の梅をイメージした「標野(しめの)」(151円)。アルコールを飛ばした梅酒を寒天で固めたもので、酸っぱい和菓子は当時としては画期的だった。
次第に世間に知られるようになった1973年、阪急うめだ本店のデパ地下に初出店。するとブームに火がつき、1日600万円という驚異的な売り上げをたたき出したのだ。
ついた偉名が「和菓子のソニー」。当時を知る阪急阪神百貨店の北部公彦取締役は「和菓子のソニーというより、それ以上だった」と言う。
初代・清次の後を継いだ長男の清邦もまた、異色の経営者だった。菓子作りと農業は一体だと考えた清邦は1985年、「寿長生の郷」へ本社を移す。ここに清邦は「炭焼き窯」まで作る。できた炭は茶室や休憩所で使われている。

新商品が続々登場~伝統と革新が生む極上和菓子
職人出身の芝田は社長就任以来、新商品の開発を加速させている。
春の新作は、一番人気の「あも」の求肥にヨモギを練り込んだ、「あも蓬」(1296円)。さらに求肥と餡を透明な寒天で2層にした涼やかな「夏の玉露地」(237円)、梅の甘露煮と餡をパイ生地で包んだ和洋折衷の菓子「葉守」(280円)など、芝田は新たなヒット商品を、次々と生み出してきた。
一方、和菓子の命ともいえる餡は、今も手作りにこだわる。一番人気の「あも」に使うのは、粒が大きく希少な春日大納言という品種だけだ。
和菓子市場の伸び率はここ数年横ばいだが、芝田の代になってから、叶匠壽庵は右肩上がりの成長を続けている。
「世の中にあるものでなく、本当にないものを初代は作り上げてきました。われわれ三代目もやっぱり挑戦していく。そういうスピリットというのは忘れてはならんと」
和菓子の本場、京都に芝田がやってきた。ある大物に会うためだという。現れたのは裏千家十五代家元、千玄室さんだ。初代・清次の時代から叶匠壽庵のよき理解者で、今も時折、菓子を納めている。芝田にとっては菓子作りの指針とも言える存在だという。
「叶匠壽庵も新しい創造性はいい。しかしながら、一つの『叶匠壽庵はこれだ!』という筋を通すことが商いだと思う」(千玄室さん)
芝田は、伝統と革新の両立という大きな課題に向きあっている。

和菓子の常識を打ち破れ!カリスマ創業者、誕生秘話
滋賀県大津市の住宅街には小さな店、長等本店が叶匠壽庵の創業の地だ。三代目社長の芝田は、ひまを見つけてはこの店に立ち寄っている。芝田がこの小さな店の門をたたいたのは20歳のとき。ここで初代・清次から、和菓子職人としてのイロハを叩き込まれた。
「お客様、消費者に対して正直にきちっとしたものをお作りしないといかんと。そういうところで間違ったことをすると、すごく怖かったですね」
一代にして叶匠壽庵を人気の和菓子店に仕立て上げた創業者の芝田清次は、強烈な個性の人物だったという。
清次は1919年、大津の生まれ。18歳のとき徴兵され日中戦争に従軍。敵の銃撃を受け、左目を失った。帰国した清次の残された目に飛び込んできたのは、花と緑あふれる故郷の風景。生きている喜びを感じたという。大津市役所勤務を経て、39歳のとき、故郷の自然を和菓子で表現したいと考え、叶匠壽庵を創業した。
創業間もなく職人見習いとして入社した岩岡和男(現顧問)は、清次の菓子には技術を超えた「思い」がこもっていたという。
「自分自身も戦争に行って帰ってきた。命がけという思いでしておられましたから、お菓子に対する情熱というのが半端ではなかったです」
清次が最初に作ったのが「道標(みちしるべ)」という最中。毎日、祈りながら餡を炊いたという。
創業から半年ほどたったある日、転機が訪れる。店の前に黒塗りの車が止まると、ステテコ姿の男が降りてきた。男は店に入るなり、「この前知人からお宅の最中をもらってな。あの味が忘れられないへんのや」と言う。そしてこう続けた。
「あんたのお菓子にワシは『祈り』を感じたんや。ここにあるもんを全部くれ!」
自分が菓子に込めた「祈り」をわかってくれる人がいる。そう思った清次は、涙ながらに見送ったという。
後にこの男性は、伊藤忠商事の当時の社長、越後正一氏だったことがわかる。越後氏との縁から、パナソニック創業者の松下幸之助氏など多くの財界著名人が次々とお得意さんになり、経営が軌道に乗っていった。
さらに、岩岡は、清次には優れた感性があったと言う。
「厳しいというか、感覚がすごいんですよね。今から思うと素晴らしい発想力を持っていた」
たとえば、雲の合間からから夕日が姿を現し、空が見事なピンク色に染まったある日。清次は職人たちにその光景を見せながら、「あの夕日のイメージをお菓子に!」と言った。岩岡は卵白や食紅で夕日を表現した「鄙の艶(ひなのつや)」を考案、ヒット商品になった。
また、ある日、宴会に招かれた清次。宴もたけなわになったころ、芸者がつまずき、胸が偶然、清次の手に当たった。「この柔らかい感触を、お菓子にしたい!」と、清次。このときも岩岡はすぐに試作品を作ったが、「わしが求めているのは、こんなお菓子やない。やり直しや!」と怒鳴られたという。
「自分が感動しないお菓子はお菓子じゃないという思いがあるので、その場で下に投げられたり、ぶつけられたり……やわらかい餅のお菓子ができましてね。そのときは泣いていましたよね、感動して」(岩岡)
岩岡はゆずのジャムを寒天と餅でくるみ、清次のイメージを形にした。

自然と菓子作りの融合、そしてカリスマ経営を超えて
1982年、長男・清邦が2代目社長に就任。叶匠壽庵の基盤を、より強固なものにしていく。
清邦はときに父・清次と対立しながらも、「農工ひとつ」の理念を掲げ、和菓子づくりの理想郷、「寿長生の郷」を作り上げた。さらに、デパ地下などへの出店も拡大。叶匠壽庵を全国区に仕立て上げたのだ。
二代に渡る強烈なリーダーの跡を継いだ芝田は、カリスマ経営とは違う道を、目指しているという。社員を前にたびたび口にする言葉がある。
「叶匠壽庵は道のないところに道を作る精神で、初代、二代はやってきた。自分の力ではできないが、皆さんの力を借りれば、ひょっとしたら会長(二代目)より大きいことができるかもしれない」
三代目になって5年、社内に変化が起きているという。社員たちからは「社長の方が先に自分の意見を言われるのではなく、『どう思う?』と言っていただけるのは、前とは違うところかもしれない」「初代と二代目がカリスマ的とおっしゃっているが、みんなの力を集めて一つにすればそれに負けないぐらいのパワーを持っていると言ってくれているので、風通しも良くてやりがいは上がっていると感じます」という声が聞かれた。
社員の総合力で、叶匠壽庵はさらなる発展を目指す。
和菓子の未来を切り開く~若手女性職人の挑戦
芝田は、和菓子の将来に危機感も抱いていた。同じ菓子業界でも、洋菓子を作る職人、パティシエはいまや若者に人気の職業。それに比べて、和菓子職人を目指そうという若者は、どんどん減っているのだ。そんな中で芝田はある取り組みを始めた。
職人が和菓子の材料を延ばし、作っているのは花びら。これは工芸菓子と呼ばれている。工芸菓子とはお菓子で作ったいわば彫刻のようなもの。鳥や花などのすべてが、砂糖やモチ米の粉など、和菓子の材料でできているのだ。
叶匠壽庵の工芸菓子の第一人者が、職人歴50年の山川正(現顧問)。山川は1978年、パリの砂糖菓子博覧会で日本人初のグランプリを獲得。そのときの作品「金鶏と牡丹」は、世界の菓子職人から賞賛を浴びた。
芝田は工芸菓子に挑戦することで、若い人へのアピールにつなげようと考えたのだ。
目指すは4月下旬に三重県伊勢市で開かれるお菓子の全国博覧会。大会に向けて、中堅の職人と期待の若手職人からなる、専門のチームが編成された。
「工芸菓子は全ての技法が盛り込まれています。麺棒で伸ばす、生地をぼかす、色を合わす。これをやることによって立派な職人に成長するんです」(芝田)
赤坂プリンス跡地に建つ「東京ガーデンテラス紀尾井町」。ここに去年オープンした叶松寿壽庵の新店舗がある。この店で人気を呼んでいるのが、和菓子としては珍しい実演販売。四角く固めたつぶ餡に水で溶いた小麦粉の生地をつけ、軽く焼く。「きんつば」だ。
これを焼いているのが、今回、工芸菓子のメンバーに呼ばれた江口綾(27歳)。江口はもともと画家志望だったが、和菓子づくりの魅力を知り、叶匠壽庵に入社してきた。
「工芸菓子はすごくやりたいと思っていて、郷の自然を感じるお菓子を作るのが、本社に帰ってからの目標です」
3月下旬、工芸菓子の制作チームに江口も合流した。指導するのは工芸菓子のレジェンド、山川だ。江口が教わっているのは花の制作。砂糖でできた材料で薄い花びらを作って貼り合わせ、形にしていく。山川の指導ででき上がったのは可憐な「野牡丹」の花だった。
4月下旬、三重県伊勢市。工芸菓子展に参加する叶匠壽庵の職人たちの作業が大詰めを迎えていた。ベテランに交じり、若手菓子職人、江口の姿も。山川の指導のもと、最後の仕上げを行っている。江口が初めてつくり上げた「野牡丹」を挿す。
ついに一ヶ月半かけた労作が完成した。作品名は「御花献上(おんはなけんじょう)」。開催地の伊勢にちなみ天照大御神に献上する花束をイメージした。これぞ和菓子の真髄だ。
「今まで和菓子をあまり食べなかった方にも、和菓子食べてみようかなと、触ってみたいなと興味がわいてもらったら、嬉しいなと思いますし、そう思っていただけるような和菓子づくりをしていけたらなと思います」(江口)
~編集後記~
和菓子には、西洋のケーキのような派手な装飾性はない。だが、小宇宙を内包しているかのような、複雑で繊細な製法で作られる。
滋賀・大津を本拠地とする「叶匠壽庵」は、京都へのリスペクトと対抗心を持ち、創業者は個性と創造性を発揮し、二代目は広大な里山を持つ敷地に、思想を反映させた。
三代目の冬樹さんは、理念を継承しながら、従業員の視線で社内の結束を固め、経営を万全にした。
「農工ひとつ」。土を耕し、自然に逆らうことなく、日本古来の伝統とモダンな創造性を両立させ、和菓子という小宇宙を開拓し続けている。
<出演者略歴>
柴田冬樹(しばた・ふゆき)1964年、滋賀県生まれ。1984年、叶匠壽庵に入社。2012年、三代目社長に就任。


