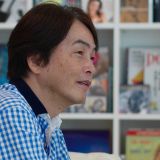石田衣良ブックトーク
『小説家と過ごす日曜日』
2016年9月23日 Vol.30
【ごあいさつ】
本を書くのが作家の本業だけど、もっとライブに新しい発信はできないか?
世界は日々動いているのに、一冊の本をつくるまで2年はかかってしまいます。
このメルマガは、ぼくが考えたこと、感じたことをありのままに伝える新しいメディアです。
この国の本の世界をすこしでも変える第一歩になれば、最高にうれしいです。
感想、反発、いい素材、どしどしメールしてください。
明日は誰にもわからない、それなら笑っていきましょう。 石田衣良
00 PICK UP「前向きになれる本を教えてください」
今回紹介した本の作者はイギリス人。やっぱりイギリス人って、大英帝国を作ったおかげで、世界のことを全部見ておくと得になるっていうことが分かっているんだよね。みんなも鳥瞰的な「イギリス人の目」を持っておくといいんじゃないかな。
▼Q▼
42歳男です。妻と2歳の子どもと暮らしています。石田さんの「世間の価値観にはまっていると落ちていくことになる」との言葉が印象的でした。読書をすることによって、自分の価値観を見つめ直していきたいです。
しかし、やることに追われすぎていて、じっくり感情を味わえなくなっている自分、正解を求めてしんどくなっている自分がいます。漠然とした不安と付き合いながら、人生を生きて行くことに前向きになれる本を紹介してくだされば、嬉しいです。
【A】
こういうことを考えると、偽物の幸福とか理想を売る、たちの悪い自己啓発の本にはまっちゃう人が多いんじゃないですか。でもやっぱりそこに安定はないんだよね。瞬間的に効くある種の痛み止めみたいなのはあるんだけど、それではダメなので。
もし本当に真面目に考えるのであれば、人間の歴史を俯瞰してみたらどうですか。ぼくがいま読んでいて、すごくおすすめの本があるんですよ。『137億年の物語─宇宙が始まってから今日までの全歴史』という本なんですけど。ビッグバンから始まって、現在にいたるまでの137億年の歴史がすべて入っているんです。4段組なのでかなりボリュームあるんですけど、おもしろい!
ひとつ感動したことがありました。いまから530万年前、地中海は干上がった塩の層が何十メートルもたまっている盆地だったんです。ある日、スペインとモロッコの間(現在のジブラルタル海峡)をふさいでいた山脈がバコッと割れます。そこから大西洋の海水が流れ込んで洪水になりました。
いまのナイヤガラの滝の数十倍以上の落差の超巨大な滝が流れ続けたんですから、モーゼの十戒なんてレベルじゃないですね。地中海がまるまる入るくらいの大きさだから、それこそ全地球の海面が何センチか下がるぐらいの規模です。それが10日くらい続いたんじゃないかな。いやぁ~、10日間の大瀑布、見たかったね~。記録にはまったく残ってないんだけど(笑)。
そんなのを読むと、「な~んだ。人の一生なんてほんとにくだらないし、取るに足らないな」って思いますよ。「でもその中で、みんな幸せになろうとして生きているんだな」っていう、それぐらいの視点で自分のことを見ればいいんじゃないですかね。みんな自分の人生ばっかり大事に思い過ぎているんだよね。大したことないよ、みんなチョボチョボなんだから。
アレキサンダー大王も42歳会社員も一緒です。どちらにしても死んじゃうので。もうちょっと巨視的な視点と、いまの自分の生活っていうのをうまく折り合わせるような考え方がいいんじゃないですかね。それと「前向きだったら大丈夫」っていう、ブラック企業みたいな考えも良くないよね。「自分の可能性は100パーセント達成しないといけない」とか。「なんでそんなことしないといけないの?」って思います。
夢とか絆とか、底の浅い言葉でなく、自分と世界について考え直してください。
『137億年の物語─宇宙が始まってから今日までの全歴史』
(文芸春秋)
[著] クリストファー・ロイド
今週の目次
00 PICK UP「前向きになれる本を教えてください」
01 ショートショート「ぼくの映画館史」
02 イラとマコトのダブルA面エッセイ〈30〉
03 “しくじり美女”たちのためになる夜話
04 IRA'S ワイドショーたっぷりコメンテーター
05 恋と仕事と社会のQ&A
06 IRA'S ブックレビュー
07 編集後記
01 ショートショート
映画館というとみなさんはどんなイメージが浮かびますか。
先日六本木ヒルズにあるシネマコンプレックスで最先端のCGを駆使したアニメーションを観ていて、ふと不思議に思いました。
その昔、映画館でたべたのはこんなにおいしいキャラメルポップコーンじゃなかったなあ。出来立て熱々ではなく袋にはいった冷めた塩味のポップコーンだった。
そのときぼくが今まで映画を夢中で観てきた映画館を書いておこうと思ったのです。
モノクロームの映画でもゆっくりたのしむようにお読みください。
ぼくの映画館史 石田衣良
記憶にあるもっともふるい映画は、大映の「ガメラ」シリーズだ。
当時ぼくは6~7歳。テレビで放映中の特撮番組が大好きだった。
世はSF、怪獣の大ブーム。図書館の児童室では黄金期のアメリカのSFを探しては読み散らしていた。
その小学校のすぐそば、ボーリング場のとなりにぼくの記憶上もっとも古い映画館があった。東京の下町には歩いていけるところにいくらでもちいさな映画館があり、テレビをしのぐ娯楽の王さまとして、街の中心として輝いていたのだ。
ガメラの広告看板は子どもの目から見ても迫力はあるがへたくそで、それが妙に味があってよかった。タイル張りの床はところどころひび割れ湿った感じで、赤いベロア張りの座席はだいぶ疲れた雰囲気だった。だが、それでも十分映画館は豪華な場所だったのである。なにせ、そのころは下町の商家にソファなどというおしゃれなインテリアは存在しなかったのだ。
ぼくはそのちいさな映画館で、大映の特撮ものや大量のマカロニ・ウエスタンなどを観ていた。どんな映画も手に汗にぎるほどおもしろかった。暗闇のなか光と影と音に集中し、外の世界、小学校のつまらない教室や平凡な自分の家のことをすべて忘れることができるのだ。
映画はほんとうに、エスケープ=脱出の王さまだった。
小学校高学年になると、ぼくの足はぐんと伸びる。
距離にしたらほんの10数キロ、国鉄をのり換えて20分ほどだが、文化的には一気に辺境の地から時代の最先端へ。
最初は父といっしょにでかけた有楽町の映画館だった。そこで007シリーズを観たのだ。うわあ、都心の映画館はおしゃれだなあ。ロビーのカーペットは深々としてやわらかく、客席にはトイレのにおいがしない。映画を観にきている人も、みな着飾っている。カウンターのむこうには見たことのない飲みものや輸入菓子が売っている。
翌月から、ぼくはひとりで有楽町にいくことになった。そのころ祖父が東宝の株主で、毎月のように株主優待の無料チケットが送られてきたからだ。祖父はずいぶんな年で、自分で映画を観にいくことはすくなくなっていた。余っているのなら、ぜひぼくにください。