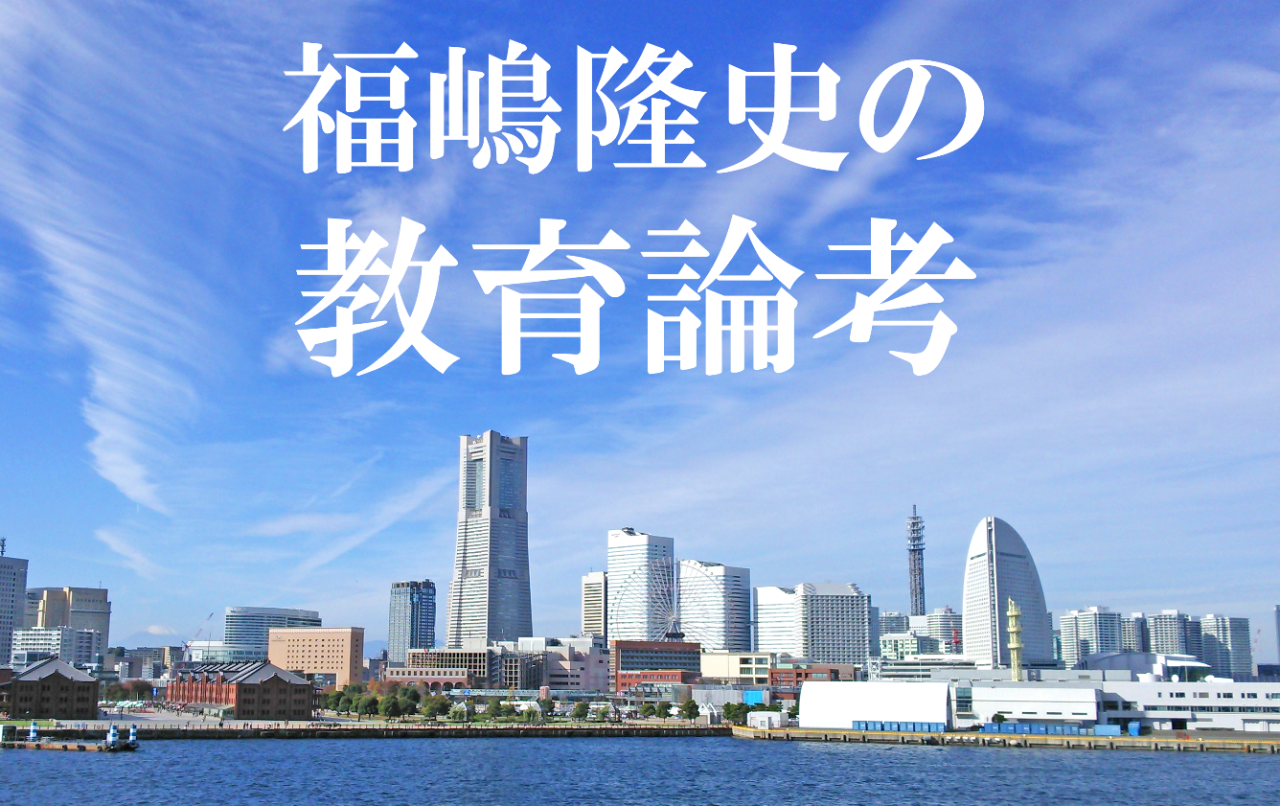
~ 第1志望校に合格できなかった子と、そのお母さんお父さんへ ~
この2月の中学受験も今やすっかり終わり、小学6年生とそのお母さんお父さんは、よかれあしかれ、力の抜けた状態でお過ごしのことと思います。本当に、お疲れさまでした。
第1志望校に合格できなかった子、そしてその親のみなさんの中には、もう既に終わったこととはいえ、やはりまだ時折、「あのときこうしていれば…」「あれがいけなかったのか…」などなど、心の中に訪れる後悔の念を振り払うのに苦労している方も、いらっしゃるかもしれません。
そんな方に、次の言葉を贈ります。
鶏口となるも牛後となるなかれ
言わずと知れた言葉です。
牛の尻尾についているより、鶏のくちばしとなれ。
ハイレベルな集団の中で「最後尾」についているよりは、たとえそれがワンランク下の集団であっても「リードする立場」にいるほうがよい。
そういう意味です。
希望通り、第1志望のハイレベルなA中学に入学できていたとしたら、今はきっとハッピーでしょう。
しかし、当然のことながら、その中学に入ってからは、ハイレベルな生徒たちに囲まれながら、ハイレベルな授業を受けることになります。
それは、とりもなおさず、「落ちこぼれてしまう」「相対評価(要するに順位)が下がる」といった危険と隣り合わせになる、ということです。
現に、レベルの高い中学に入学したのはよかったのだが、授業や定期テストが難しすぎてついていけないとか、周囲の生徒の能力が半端じゃなく、劣等感に悩まされ始めているとか、そういう話をよく耳にします。
「何を言っているんだ。うちの子は、もし受かっていれば、最後尾になんかならないぞ」
そういう声も聞こえます。
もちろん、その可能性はあります。
しかし、可能性としては、学年の中で中位~低位に位置するようになる可能性のほうが、若干高いでしょう。
それよりは、第2志望の学校でしっかり頑張って、学年の中で上位に位置していたほうが、ずっといいのではないでしょうか。
実は、これは、実際の体験に基づく話なのです。
何を隠そう、私自身の体験です。
私は、自身の中学受験において、第1志望も第2志望も落ちました。
第3志望の攻玉社中学校に入学しました。
普通なら、落胆したり、意気消沈したりするところなのでしょう。
しかし、私は、とくに落胆も消沈もしませんでした。
新しい中学生活を意気揚々とスタートさせました。
そして、1学期の中間試験は、学年200名強の中で、1位でした。
ほぼ、全科目1位。
10教科近くの平均点が、96点くらいでした。平均点が、です。
中学に入ってから塾に通ったわけでもないし、特別な勉強をしたわけでもありません。
単に、日々真面目に勉強し、真面目に授業を受け、真面目にテストに臨んだ結果が、それだったのです。
期末も、総合3位。
その後、高校3年生で卒業するまで、上がり下がりはありましたが、平均して、学年200名強の中で20~30位以内をキープしていました(1位をキープするのは無理でしたが)。
結果として、学力別のクラスでも、高3までずっと、特別クラスに在籍することができました。
私立中高の先生方は、優秀な生徒をほしがっています。
これは、当然のことです。
だからこそ入試を実施するわけです。
そんな中で、1位~30位くらいの生徒は、当然ながら、先生方からも高く評価されます。
何かにつけて、ほめてもらうことも多くなります。
学級の中で、普通に先生方にほめてもらえるだけではなく、朝礼の壇上で全校生徒の前で表彰されたり、コンテストで入賞したり……そういう機会が、必然的に増えていきます。
そうしてその生徒は、学校の中での自己の存在価値を実感し、自己の重要感を高めていくことができるようになるのです。
もし、第1志望のA中に入っていたら、もしかしてもしかすると、その逆を歩む結果となった可能性があります。
そう考えると、どうでしょう。
第2志望で、むしろよかったのではありませんか?
もっと言えば、第2志望も第3志望も全て落ちて、地元の公立中に通うことになったのだとしたら、自己の存在価値を実感できるこうしたチャンスは、最大限に高まるのです。
こんなに楽しみなことは、ありません。
意気揚々と、公立に通い始めてください。
私は、先に書いたように、多くの先生方にほめてもらいながら、6年間を過ごしました。
中2のときには、英語スピーチコンテストで学年3位。
高1の6月には、英検2級に合格して表彰。
高3のときには、読書感想文コンテストで最優秀賞。
そして、先生方への感謝と尊敬の念も、高まりました。
これは、自慢でもなんでもありません。
第2志望校、第3志望校に入学することになり、やや落胆気味の子どもたちの未来にも、同じようなチャンスが広がっています。
もし第1志望に進学したらかなわないかもしれない多くのチャンスが、待っています。
私は、私の事実を書くことで、それを伝えたいのです。
自己の重要感を得ることは、何にもまして、成長のエネルギー源となります。
今や世界の誰もが知っている名著『人を動かす』の著者、デール・カーネギーは、その中で、心理学者ウィリアム・ジェームズの言を紹介しています。
「人間の持つ性情のうちで最も強いものは、他人に認められることを渇望する気持ちである」
そして、こう続けています。
「ここで、ジェームズが希望するとか要望するとか、待望するとかいうなまぬるいことばを使わず、あえて渇望するといっていることに注意されたい。これこそ人間の心を絶えずゆさぶっている焼けつくような渇きである」
この、他者に認めてもらいたいという気持ちが充足され、自己の重要感が得られたとき、人は、変わるのです。
私がもし、今から33年前の2月、第1志望の中学校に合格していたとしたら……重要感を満たされる機会が減り、不満を抱きながらの中高生活を送る結果になったかもしれません。
そして、早稲田大学に入学することもなく、まったく別の人生を送ることになったかもしれません。
中学入試は、たしかに、人生の転機です。
しかし、第1志望に受かることが、イコール、最高の転機であるとは、言いきれないのです。
そうそう、もう1つ。この故事成語を知っていますか。
人間万事塞翁が馬
もともとの意味は、ググってみてください。
要するに、人間(じんかん=人の世)では、あるできごとの価値がいつ逆転するか分からないから、必要以上に喜んだり悲しんだりしないほうがよいという話です。
ぜひ、前向きに。
明るい未来が、きっと、待っていますから!!
(この文章は、2009年に配信したメルマガの内容に一部加筆したものです)
