こんにちは、結城浩です。
村上春樹の新刊『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』が刊行されて、結城もさっそく読みました。以下、ネタバレ的なものはほとんどない(はずの)感想です。

◆『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』(村上春樹)[ペーパーバック]
村上春樹の新刊が出るというニュースで最初に驚いたのは、「書名が公開されていないのに予約開始」という状況でした。結城はアマゾンで予約して、刊行日の次の日くらいに入手し、一気読みをしてしまいました。
村上春樹全集に挟まれていたブックレットで読んだと記憶していますが、村上春樹は長編のあいだに中編や短編を書いて、いろいろと「実験」をしているようです。たとえば『スプートニクの恋人』を書いたときには、文章の「ネジを締める」練習をしていた、というようなことが書かれていました(いまは記憶で書いているので正確ではありません)。「ネジを締める」というのは、無駄な言葉を廃して、文章をキチキチに短くしていくという練習(実験)ではないかと想像しています。
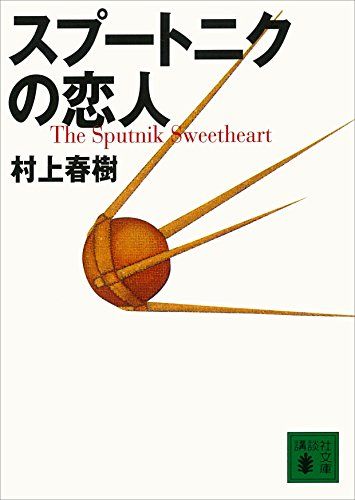
本を書く身として、そういう「実験」を行いたくなる気持ちはよくわかります。自分の書く技術を向上させる。そして本が作り出す世界を広げる。そのためには文章を書いたり、本を構成する上で、新しい技法を試すことが必要になります。
そういう実験を行うときに問題になるのは、すでに存在する読者さんです。読者の多くは「これまでと同じようなもの」を求めます。しかし、新しい技法を試すということは、多かれ少なかれその期待を裏切ることになるでしょう。さもなければ、新しい技法ではありませんからね。
もちろん、新しい技法を試すからといって、自分のすべての読者をがっかりさせるわけにはいきません。その一方で、自分のすべての読者の(これまでと同じものを読みたい)という期待を満足させることだけを考えていては書き手としての進歩も広がりもないわけです。
そのようなせめぎ合いは非常によく理解できます。村上春樹は現代日本の作家として世界的にも注目され、また商業的にも大きなインパクトがある立場です。その中で新しい技法を試すのは(もしそういうことを今回も試みたとすれば)、たいへんチャレンジングなことであると思います。
村上春樹と自分を比べるのはたいへんおこがましいことではありますが、結城も新しいチャレンジをいつも考えていきたいと思っています。すでにいる読者さん全員にがっかりされることは避けつつも、あえて新しい分野や、新しい技法や、新しい「何か」を探りつつ、進んでいきたいと思います。
さて、村上春樹の『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』に戻りますが、全体としては「いつもの村上春樹」という内容でありながら、あちこちに「あれ?」や「ふむふむ?」のようにひっかかる部分を感じつつ楽しく読むことができました。村上春樹のような作家になると、おそらく「読み手がすぐに気がつくこと」はすべて意図的になされているはずです。ですから結城は、
「どうしてこういう書き方をしたのだろう」
「どうしてここまで踏み込んで書いたのだろう」
という書き手のメタな立場で読み終えることになりました。
◆『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』(村上春樹)[Kindle版]
(結城メルマガVol.055より)
