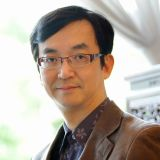●イントロダクション
※この部分は無署名原稿ですが、「総論」はこの原稿と同じパンフレットに載っていることを前提に書いているので、同時収録します。なお、他のストーリー部分、用語事典などは割愛しました。
ガイナックス20周年を記念し、ついに《バスターマシンSAGA》が完全合体。劇場へ飛び出した! 『トップをねらえ!』と続編『トップをねらえ2!』を各々約90分の劇場映画に再構成、一挙上映するのがこの企画である。物語と現実と……2つの時空を超えて、銀河系を横断する雄大なサーガがひとつにまとまるとき、まだ誰も知らない感動が銀幕に結晶化する。
時に1988年――OVA(オリジナル・ビデオ・アニメ)の世界に『トップをねらえ!』が燦然と登場した。後に『新世紀エヴァンゲリオン』('95)を世に放つ庵野秀明の監督デビュー作である。製作は前年、劇場映画『王立宇宙軍 オネアミスの翼』(監督:山賀博之)』で誠実かつ高密度なアニメーション映像を提示し、歴史を書き換えたクリエイティブ集団ガイナックスだ。
キャラクター原案に美少女キャラで著名な美樹本晴彦、メカニックデザインにスタジオぬえの宮武一貴と『超時空要塞マクロス』のヒットメーカーを迎え、アニメファンのハートをキャッチ。さらに絵コンテ・設定に樋口真嗣(『ローレライ』監督)、ロボットデザインに大畑晃一(『爆裂天使』監督)、設定・エンディング イラストレーションは前田真宏(『巌窟王』監督)など、後にエポックメイキングな作品を送り出すクリエイターたちが結集。まさに才能の総力戦とも呼ぶべき作品が登場した。
当初パロディ色の強いところからスタートした『トップをねらえ!』は、物語が進むにつれてスケールがぐんぐんと拡大。舞台も沖縄の女子校から銀河系規模へと壮大なものとなり、ストーリーも情熱的になっていく。今回の劇場版では大スクリーン上映によって、ビデオでは不鮮明だったディテールが見えてくることで、眩惑感を覚えるほどの興奮が余すところなく伝わる。特に悠久の時空を超えて達成されるラストの展開は、必ずやSF的な感動と涙を呼ぶに違いない。
時代は流れ、現実世界でも21世紀となった2005年――この作品に、10数年間にわたって切望されてきた続編が登場する。それが同じくOVA全6話の形式で製作された『トップをねらえ2!』である。
原案・監督は『フリクリ』で先鋭的な感覚に充ちた新世代アニメを提示し、大きな話題を呼んだ鶴巻和哉。脚本は、同作で鶴巻監督と絶妙なコンビネーションを見せた榎戸洋司。キャラクターデザインは『新世紀エヴァンゲリオン』を担当、第1作の『トップ』スタッフでもある貞本義行。フューチャービジュアルはokama(『ひまわりっ!』)、バスターマシンデザインは いづなよしつね(『ガドガード』)、メカニックデザインは石垣純哉(『鋼の錬金術師』)と、最先端のビジュアリストたちを結集。映像面で、第1作目とは刷新された印象を与え、新たなファンを獲得することに成功した。
その一方で、企画監修には庵野秀明、絵コンテに樋口真嗣とオリジナルの中核メンバーがポイントを押さえた上で、田中公平の音楽がパート1とパート2を共通のメロディーで橋渡しするという、絶妙な仕掛けが施された。そう……これは紛れもなく、正統なる続編なのである。
お姉さまと慕う天真爛漫な少女。太陽系の片隅からスケールが次第に拡大、驚くべき大逆転が待っているところなど、ふと気がつけば、さまざまな事象がパート1との相似形を描き出す。その頂点となるクライマックスの超絶バトルシークエンスの頂点では、あっと驚く両作品の関連が現出する。この感覚、まさにセンス・オブ・ワンダー!
こうして誕生した2つの作品は、時間を接して濃縮状態で鑑賞されることで、新たなる共鳴の感覚をスクリーンに醸し出す。
時空を超えた感動体験が、いまここから始まる!
●総論本文
題名:濃縮された3時間がもたらす体験
文:氷川竜介(アニメ評論家)
改めて言うまでもないようなことだが、『トップをねらえ!』('89)という題名は『トップ・ガン』と『エースをねらえ!』の合成である。当初、そのタイトルをまるで裏切らないパロディ色(お姉さまの鉄ゲタ等)と商品性(ノリコたちの露出の多いコスチューム)から第1作目はスタートした。それはアニパロ(アニメパロディ)をさらにパロディ化するような毒性の強い作風で、その入り口も今にして思えば実はトラップだったのだが、まんまとそれに引っかかってラストシーンで感動の高みに連れていかれたときの驚きと高揚感は、現在も色あせていない。
世紀を超えて製作された続編『トップをねらえ2!』('04)も、そういう点では同じような韻を踏んでいる。現代的な萌え、ポップカルチャーを意識したようなビジュアルを多用し、ストレートな続編を避けて最新型にチューンしたように見せながらも、同じような階段を登って風呂敷を拡げ、壮大な感動の高みへ誘うという構成をとり、見事に2本で1本というラストへ着地するアクロバティックなパート2のあり方を見せてくれた。
両作ともOVA(オリジナル・ビデオ・アニメ)の歴史に残る大作であるのは間違いない。そして今後語られるときには、こうした2作の関係性が必ずや意識されるはずである。そこにダメ押しのように登場したさらなるボーナス的なプレゼントが、今回の「合体劇場販!!」である。
「思えば遠くへ来たもんだ……」というのが率直な感慨で、それは劇場に足を運んだ観客の方々にも共通していることではないだろうか。
ここではこの「遠く」という言葉が心のどこか引っかかる感覚を手がかりにして、この「合体劇場版!!」を総括してみたい。
日本の商業アニメーションの歴史は、劇場映画主体で始まった東映動画(現:東映アニメーション)と、それに対してTVアニメを立ち上げた手塚治虫の虫プロダクションの2社が大きな源流に位置する。これにリアル色の竜の子プロダクション、CMの流れをくむエイケンなどが加わり、特色のあるプロダクションの文化的な流れをもっている。
その個性は今でも幾多のアニメ製作会社へ受け継がれているが、継承される個性の現れ方は「いかにビジネスを成立させるか」という点に大きく引きずられている。言い換えれば「大人が子どもにアニメをどう提供するか」という高低差が根にある。
ところがガイナックスは、アニメ製作会社としてはそれとは観点が異なっているように思える。「送り手と受け手が同じ地平に立っている」という、よりフラットなイメージが強い。もちろんクリエイターの誰もが商品をつくっている以上、受け手のことを考えるのは当然にせよ、ガイナックス作品には一方通行でなくもっと共犯性の高い作品づくりをしたものが多い。それがもっとも顕著に出たのが『トップをねらえ!』2シリーズの作風と言えるのではないだろうか。
「観客の立場から作品をつくる」という性質は、ガイナックスの発祥にも起因しているものである。ガイナックスとは1987年公開の『王立宇宙軍 オネアミスの翼』のために作られた会社だが、前身はSF大会中心に活動したアマチュア集団「ダイコンフィルム」だ。古今東西のSFキャラクターが一同に介するオープニングフィルムはすでに伝説だが、パロディ、オマージュを混淆した上でクリエイションの燃料とし、熱い情熱へと昇華させるという点で、『トップをねらえ!』は、やはりその原点のテイストにもっとも近くにあると言える。
こうした論考を踏まえて、考えを深める上で欠かせない重要キーワードが「オタク」である。「オタク」は本来は趣味性が高じてなるものだから、「濃度」が上がれば個に集約して内向しがちな性癖をもつはずだ。それなのにガイナックス的な「オタク」とは、もう少しステップアップしたものを志向していると思える。仲間とのコミュニケーションや集団作業経験を経て、表現という外向的なエネルギーに転化し、面白さの発見に転化していこうとしているから、どこかが違う。
この「違い」は出発点としてはささやかなものだが、ゴールを大きく変えるようなものだ。先述のような伝統的なアニメ会社とは別枠にあるという「隔たり」を感じさせるような作品の手ざわりもその「違い」の結実だし、オタクが抱きがちな自己嫌悪にまみれた内面に向けて「本当は違うものがあるんだろう?」とささやき、共犯関係を誘う。だからこそ「遠く」に行くことも可能になる。
このようにして「遠くへ行く」図式は、作中からも見いだすことができる。たとえば第1作の『トップをねらえ!』の初期では性格的に天然風の少女に過ぎなかったタカヤ・ノリコが、途中からは「宇宙一のオタク」ぶりを発揮するようになる。スタッフのシャレの産物でもあるから100%真に受けるわけにはいかないにせよ、案外そうした部分に重要な本音や核が見えるようにも思える。
それは、彼女が「オタク化」するのと「本気になる」のとが、ドラマ的なタイミングとしてほぼ完全同期しているからである。
死や恐怖という現実の壁にぶちあたり、内向しようとするあらゆる自分の弱さを克服して火と燃やし、尊敬する「お姉さま」の心にも火をつけて対等なパートナーに成長、ともに「炎」となって人類を救うノリコの姿は実に感動的だ。それは『トップをねらえ!』という作品を触媒にして、オタク魂を燃やしつくしたスタッフの気持ちがフィルムに焼きついているから、観客のわれわれオタクたちもまた感動の彼方へ導かれるのである。その感動とは「オタク」の内面に等しく存在していたものなのだ。
「遠く」という言葉に反応するのも、ノリコとともに戦っているうちに、連れて行かれたあの高みへの距離感によるものなのだろう。
このようにして、送り手・受け手が同じ地平に立ち、共鳴を起こして感動の彼方へ誘われるというような現象は、至高のカタルシスと言えるのではないか。なおかつその共鳴の仲介をすべき作中キャラまでが、相似形を描いた構図と地平に立っているとなると、これはきわめて稀少な事例であるようにも思える。
ノリコたちの情熱の結果は、1万2千年という悠久の時をジャンプすることさえ可能であった。その飛翔はフィクションに内向せず、現実世界でも作品が20年近い大いなる時間の壁を突破することに成功している。
こうした非現実的とも思えることが可能になる秘密とは、「オタク精神の共鳴性」にこそあるのだ。
さて、このようにして「オタク像の共鳴性」が『トップ!』の作品静の根幹を貫いているという前提に立って、なぜ『トップをねらえ2!』が作られたのか、「1を2」を対として同時に劇場公開されなければならなかったのかを考えてみると、また少し面白そうなものが見えてくる。
いま、時代は西暦2000年代――これまでさんざんSFの世界で描かれてきた21世紀が現実となった世界である。だがよく考えてみると、かつてはるか遠く高みに昇れたはずの「オタク」の姿は、いつしか劣勢になってしまったようにも思える。
それは『トップ2!』で「赤い天の川」によって太陽系外の「遠く」へと隔絶された人類の姿のようで、冷ややかな閉塞感をともなっている。
その中でヒーロー、ヒロインとして活躍しているトップレスが、子どもだけに許された超能力をもつ者の集団だという設定は、実に興味深い。それもまたある種の「オタク」の自画像のように思えてくるからだ。
トップレスは、想像力を媒介にした能力で現実の物理法則を歪曲し、通常兵器ではなしえないような現象エキゾチック・マニューバを起こして戦闘を行う。それはまさにアニメーションだけが可能にする表現で、説得力をもつ作画表現で入念に映像化されている。こうしたことが可能な者のもつ、一種の傲慢さ、反社会性もまた、トップレスの特性であり、それは現実世界の「オタク」の一部の性癖、あるいは常に観客におもねらず、他者をぶっちぎって自己に忠実な作品づくりをしてきたガイナックスの姿とも重なる。
では、トップレスはオタクの願望を叶えるような無敵万能な理想の存在として描かれているのかと言えば、それはそうでもない。加齢による「アガリ」を迎えることでトップレス能力は喪失し、大人の一員にやがては組みこまれてしまう者も多い。さらに変動重力源を利用して、そのルールの禁忌を破ろうとした者の末路を考えると、「オタク」が夢想しがちな無制限な自由を、決して良しとしているわけではないのだろう。
そうした認識を踏まえた上で、では真のトップレスを目ざすノノやラルクはどうするのか……というのが『トップ2!』のドラマの真髄である。一見オバカにもとらえ得る入り口から、壮大なクライマックスの彼方へと導かれるサイズ差の高みがダイナミズムをもたらし、『トップ!』シリーズならではの大河ドラマ的な構成が、ある種の回答を提示する。それは単に設定的に2作がつながったということを超えて、1作目と2作目の間に発生する同じ種類の感動がもたらす共鳴性であり、それを手がかりにしてより高く、遠くへ心を飛翔させることも可能なものなのだ。
魂は無限の自由と想像の高みを目ざしながらも、われわれの肉体は時間や空間という現実の物理法には束縛されている。しかし、それでもなお……遠くへ、高く……と願うのが「オタク」の本質であると仮定してみよう。
その上で、1作目の目ざしたもの、2作目の目ざしたもの、2作の関係性、送り手・受け手の共犯性、共鳴性、そうした諸々を同時に脳裏にセットし、実はすべてが同じベクトルを示すものだとして、ぎゅっと圧縮してみよう。
そこにひとつの「合」をイメージできれば、壮絶なビジョンが生まれるはずだ。その力は、現実世界に作用して変革させるものではないか。
映画とは1本のシリアルな時間軸に乗って、後戻りのできない「経験」を与えてくれるものだ。『トップ!』2作の中に濃厚に埋めこまれた種々の要素が、約3時間という限られた時間の中に展開する。そのとき、何かしら過去に感じたことのない感興が得らるはずだ。それは、脳内の中ですべてのファクターがひとつのエッセンスに凝縮し、化合して生まれる味わいなのだ。
その体感は小屋が明るくなったと同時に薄らいでしまい、戸惑いを感じるかもしれない。しかし、一度感じたものは心の中にはしっかりと根ざし、この先を生きる糧となっていくはずだ。その感覚を忘れないでいれば、われわれもまたいつかは高みに達し、悠久の時空を超えることができるだろう。
その貴重な体験を伝えるために、この作品が公開されたに違いない。
【2006年9月18日脱稿】初出:『トップをねらえ! トップをねらえ2! 合体劇場版!!』パンフレット(ガイナックス)