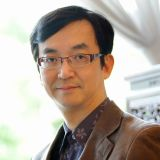もちろんTVアニメ『宇宙戦艦ヤマト』が1974年に放送されなければ、何もかもが始まらなかった。いまのようにSF的なアニメやマンガ作品が普通に楽しめる潤沢な状況もなかっただろうし、『機動戦士ガンダム』も宮崎アニメでさえ存在しない。その歴史的存在は大きい。そこにはアニメ世代の成長と、それによる市場確立という観客が主体になった時代のムーブメントが強く作用しているわけだが、ここでは経済や社会の問題には深く踏み込まず、『ヤマト』の映像作品としての衝撃の中核とは何だったのか、その根源的なものに迫ってみたい。
まず前提として理解に必要なのは、「SFは絵だ」というキーワードである。提唱者はSF翻訳家でスペースオペラの紹介者でもある野田昌宏。これは映像に限らず小説でも何でも、SF作品のここぞという場所で「感覚がジャンプ」したとき、壮大なる「絵(のようなビジョン)」が見えるという共通経験を言語化したものだ。以来、筆者としては優れたSFとはそうしたものと理解している。この日常からの離脱感は、古来「センス・オブ・ワンダー」と呼ばれているものと同質である。
『宇宙戦艦ヤマト』には、この「SFは絵だ」という感覚が明解に存在する。もちろん随所にミスも少なくないため、SFとしての全体の完成度は低いかもしれないが、そんなことはこの描かれた「絵」の大きさと美しさ、その両者が一体になって生み出される驚異のSF感覚の前には小さなこと。
では、その絵の大きさとはどのようなものだったのか? すべての始まりである、第1話を例にとって説明しよう。
第1話のAパート(前半)では主役メカのヤマトが登場しない。それどころか、まずは無関係そうな宇宙海戦から映像がスタートする。正体不明の艦隊に一方的かつ徹底的に沖田艦長と地球艦隊が惨敗を喫する場面では、宇宙戦闘の作画・演出に、それまで例のないテイストがあふれていた。
砲塔のゆったりとした動き、ビームの光芒の美しさ。被弾した艦内が非常灯に照らされ真空の宇宙に乗員が吸い出される恐怖感。これら美と破滅が背中合わせとなった感覚が、異常なまでの臨場感を生み出す。これは続くヤマトの戦闘シーン、たとえば波動砲の発射段取りなどにもに共通した感覚で、ヤマトの魅力の核心が「SFは絵」に近いことを裏づけるものである。
この宇宙戦闘と平行して、後にイスカンダルのものと判明する宇宙船が火星に落下、救命カプセルの美少女が絶命するというシークエンスで主人公の古代進と島大介が訓練兵として手際よく紹介される。この火星のくだりにしても、そこで描かれているのはやはり「美と死」だ。
このように説明抜きで緊迫した映像だけが積み重なっていくAパートは、実時間が何倍にも延伸したかのような錯覚を覚えるほどの重いストレスと、日常では絶対に見ることのできない美観をともなったスペクタクルの興奮をセットにしつつ、中CMのためにフェードアウトしていく。
仕切り直しで始まるBパート。そこで沖田の戦艦を追い越した遊星爆弾が、真っ赤に焼けただれた地球へ落下していき、表面にフレアが拡がり消えていくのを目撃した瞬間、頭蓋に杭打ち機でたたかれたようなショックが電撃のように走るはずだ。ここで生まれる衝撃感こそが、『ヤマト』における映像感覚の、最重要なものである。
論理的な説明は沖田艦長の独白に続くナレーションが経緯を語ることで提供されるが、感情的なショックは地球の全容の映像で十分だ。「まさか地球全体が破滅しているとは……」という驚き、衛星軌道上から地表レベルまでの動きを一気に見せることで醸し出されるスケール感が素晴らしい。何より重要なのは焦土を描いているはずの静謐な「赤い地球」の映像全体が、凄惨なまでに「美しい」ことである。
第1話の構成は、ここで述べたようにミクロからマクロ、結果から原因を見せることに終始し、破滅から美を連想させる手法に到るまで、いわゆる逆算式の倒叙法を積み重ねている。それはいきなり大きな絵を見せても「ふ~ん、ただ言ってるだけでしょ」という温度の低い反応しか招かないからだ。ディテールに目を引き寄せておいて、「ぶわっ!」とばかりに巨大な風呂敷を拡げてみせる。これはマジシャンが客を引き込む常套テクニックであるが、その拡大率が『ヤマト』は尋常ではなかった。何しろ赤い地球でもすでに充分すぎるスケールなのに、運命の旅路の長さは「十四万八千光年」なのだから……。人間のサイズ、人生の長さを考えると圧倒されるジャンプ感がそこに生まれるわけだ。
以上からおわかりいただけるように、『宇宙戦艦ヤマト』の魅力とは――アート的な「美」の意識と、巨視的スケールへのジャンプの感覚のセットなのだ。「美とスケール感のバランス」、これこそが要諦である。
物語的にも主人公たち青年の卑近な感覚と銀河的なスケール感、そのセットが「自分たちがやらなければ全部ダメになってしまう」という気持ちの大きさに直結している。この大きな使命感が全体に流れているからこそ、シリーズの進行も成立している。物語的にも、ヤマトの苦難の果てのゴールには「美しいもの」が待っているわけだが、それさえも「破滅の美」も含めて……という点を考えれば、映像的だけでなく作品全体に「美とスケール感」が通底していると言えるだろう。
余計なことかもしれないが、実はこの「美とスケール感」とは最初のTVシリーズに見られる一期一会的なもので、すでに再編集版の劇場映画では損なわれている。実に「諸刃の剣」的なものなのだ。『ヤマト』の続編企画や2次著作で、どことなく物足りなさや違和感を感じる場合、「美とスケール感」のバランスが損なわれているという共通点が発見できるはずだ。
たとえば「連続ワープ」などは、その典型である。最初のワープは、時空の断裂をゆったりと航行するためにさまざまな怪奇現象が見え、太古の地球の光景すらオーバーラップするという時間スケールとビジュアルのシュールな美しさ、しかしてヤマトには深いダメージを与えるという(死や負傷に近い)物理的なネガティブ結果がセットになっている実に「ヤマト的」なものであった。しかし、「性能が向上した」という説明だけで膨大な空間を一瞬で移動できるようになったヤマトは、明らかにどこかで大きな魅力を減じているのである。スケール感とは、それらしいディテールと不自由さからしか生まれないということは、忘れてはいけない。
結局、ここまでの美意識とスケール感を兼ねそなえたSFアニメは、なかなか継承者が現れかった。いま脳裏に浮かぶのは、せいぜい庵野秀明監督のビデオアニメ『トップをねらえ!』(88)のラストシーンで描かれた「一万二千年の時」ぐらいのものである。
八〇年代、九〇年代と時代が進むにつれて、「地球の滅亡と彼女への告白は等価」という、最初はギャグに近い手法で本音を露呈していたはずのテーゼが、いつの間にかコンセンサスに変節してしまった……そんな世情の推移も一因だろう。その傾向が進んだ果ての二十一世紀初頭、いまや時代は「セカイ系」である。「自分の感覚の好悪とセカイの成立は等価」という感覚からは、徹底して卑近な感覚を凄烈にジャンプする「ヤマト的なるもの」は生まれようがなさそうだ。
ただし「ヤマト的感覚」は、当時の石油ショックや公害など、行き詰まった世情の反作用として生み出されたもの。今また時代にある種の「閉塞感」があるのなら、ストレートに同ーでなくとも「ヤマト的感覚」が必要とされ、呼ばれる時代が来たのかもしれない。
そうでなければ、ヤマトの再刊本というのもあり得ないのだろうと、またあのような感覚をもつ作品の生まれる可能性を信じつつ、本稿をひとまず終えることとしたい。
【2005年3月某日脱稿】初出:「ヤマトよ永遠に MF文庫―宇宙戦艦ヤマトライブラリー」画:ひおあきら(メディアファクトリー刊)