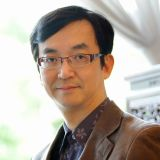●クリアな音声とド派手な色彩が喚起する本放送時の記憶
最初は買うつもりがなかったのに、ついつい手を出してしまった。「ウルトラマン the movie ULTIMATE DVD COLLECTION 1」(発売元/avex mode)も、そんなパッケージである。『長編怪獣映画ウルトラマン』(1967年7月22日公開)と『実相寺昭雄監督作品ウルトラマン』(1979年3月17日公開)、劇場映画2本をセットにした2枚組DVDだ。
どうして買う予定がなかったかというと、理由は単純だ。『ウルトラマン』の映像の基本的はTVシリーズであり、それはすでに満足のいく画質で全話DVD化が完了しているからである。今回のDVDはそれぞれ「再編集映画」としてオムニバスに近い構成を取っており、改めて1本の映画としてはどうかというと、特にプラスアルファの魅力を感じない作品であった。
パッケージングとしては、ガシャポンサイズのミニフィギュアが1体ついているのは良しとしても、プリスターパックを内蔵する関係で箱のサイズが妙に大きくなっていて、収納に困るという事情もあった。
プロモーションは非常に熱心だ。店頭で映像のエンドレス再生をしているのをいろんな場所で何度も見かけた。ことに『長編怪獣映画ウルトラマン』の方は、前回のビデオグラム化時にも思ったが、原版の状態に難があるようで、少々粒子が粗くザラザラしている。本放送終了から間もなくのことで、当時のブローアップ技術に限界があったのかもしれない。
だからなおのこと「まあ、いいか」と思ったわけだが、ある日「あれ?」ということに気がついた。
音質が良いのである……。
ビデオグラム商品では、見てすぐわかるせいか、画質の良し悪しは頻繁に問題にされる。それに比べて音質は、ほとんど話題にされない。しかし、よく聞けば差は歴然とある。今回は、セリフで差がわかった。第1話、科学特捜隊本部司令室でのフジ隊員(桜井浩子)の応答が、はっきりと抜け良く聞こえる。高域方向にすっとリニアに響く。思わず聞き耳を立てると、ムラマツキャップの声も低い方へ染み渡るように拡がりを感じ、セリフのブレスでしっかりとした呼吸の感触も伝わってくる。磁気素材の音を使っているのではないか。
フィルム制作上、セリフ、効果音、音楽とバラバラの素材は磁気テープで用意され、最終的に「ダビング」という工程で一体化される。この時点で「シネテープ」という、映像音声同期のためにフィルムの形状をした磁気テープにまとめられる。これを素材にラボ(現像所)でサウンドトラック焼き付け用の「音ネガ」が起こされる。これが光学録音だ。光の波形で音を記録するために周波数帯域が少し狭く、電話のような音なのだ。そしてダブリとなったシネテープは破棄されてしまう場合が多い。しかし、光学録音と磁気録音をラジオにたとえれば、AMとFMぐらいの音質差がある。
TVシリーズの『ウルトラマン』も現存するのは光学録音素材のみで、DVD化時に失われた帯域を補正するよう尽力されてはいたが、クリアになった映像に対して音質は「これでガマンするしかないのか」というのが率直な感想だった。ところがクリアな音声で『ウルトラマン』を鑑賞するチャンスが、まだ残っていたと知って嬉しくなってしまった。池田憲章氏が実相寺監督と撮影現場(美センと怪獣倉庫)をさまよう短編ビデオ「夢の跡~ウルトラマンの工場」(10数年前の映像特典)の復刻も収録されているというし、思い切って投資してみた。
結果は……思っていたよりも、良かった。もう何度観たか聴いたかわからない、M78星雲人(このとき固有名はまだない)とハヤタとの出会い──LPアルバム「サウンドウルトラマン」で耳に染みついたセリフも、良好な音質が新鮮な気持ちを喚起し、耳に染みわたる。素材には破損箇所があるのか、残念ながら全編が磁気録音ではないようだ。『怪獣殿下』の後半で、唐突に光学音声となってしまう部分があるが、現存部分だけでも満足度は高い。
他にも予期せぬ楽しみや新発見が多々あった。第1話相当のシークエンスでは、どのサントラ盤にも収録されていない謎の劇伴(BGM)が多数流れている。宮内國郎作曲のこの楽曲群もまたクリアな音質で聞くことができて、初代マンにも未知の領域がまだ多く残っていることに、深い感慨があった。
何度観ても驚くのが、ベムラー対ウルトラマンの対決がカットされていること。おそらく79分の尺の中で4回もウルトラマンが登場するのは多ぎるのと、構成上ここに格闘があると「序」に見えなくなるという配慮が理由だと推定している。つなぎとなるジェットビートルの移動の映像を各話から持って来ているのも驚いたが、形状のまるで違う宇宙船・白鳥を強引にビートル機と見立てている部分にはのけぞった。
構成と言えば、対ゴモラ戦が“殿下抜きの『怪獣殿下』”になっていることも改めて感心した。子どもから見た空想である怪獣世界と作品世界内でのリアルな怪獣世界が交錯する制作意図はわかるが、子ども時代の筆者は、当時かえってウソくさく受け止めて共感できなかった。それだけに子どもドラマをカットして怪獣ゴモラによる都市災害に主軸を絞ったこの編集は、実に新鮮に感じた。この変更と次作『ウルトラセブン』から「ウルトラ少年」(挿入歌に言及あり)が消えたことには共通性が感じられるというのは勘ぐり過ぎだろうか……。
色味も非常に濃く、彩度が高めに仕上がっている。黒ツブレ気味なのはモニタを調整して観たが、再現されたカラー感覚も何だかとても懐かしく感じられた。おそらく当時のカラーテレビの色調の記憶が復元されたのだろう。普及初期のカラーテレビは色実に味が派手だった。カラーフィルム初期作品の『ウルトラマン』は、本編中で色彩を意図的に強調していることが、改めて良くわかった。たとえば多々良島の植生には南方を思わせる極彩色があちこちに追加されていて、その一種毒々しくも感じる美術的配慮が、メリハリの効いた色彩でよく再現されていた。
本放送の『ウルトラマン』は、当時の子どもの大多数がモノクロで観ていたはずだ。この映画が動くカラーのウルトラマン、ウルトラ怪獣の初体験というケースも多かったと思う。その潜在的な色彩への欲求に応えようという、時代の空気ごとパッケージングされている。これはこれで格別だなと思いつつ、一気に観た。
蛇足だが、やっぱりスフランは怪獣図鑑上では「多々良島産」と「ジョンスン島産」の2種に分けなきゃいかんよなあ……などと、25年越しのよけいなことも思い出してしまった。「怪獣無法地帯」と「怪獣殿下」が直結してあったためだ。怪獣オタクは、ホントに因果なものである。
追記:その後Blu-ray化された『帰ってきたウルトラマン』の劇場公開版も音声がクリアであった。もしかしたら同時代的に残されていたシネテープから劇場用の35ミリによる音ネガを作成したことにより、記録サイズが大きくなって音質が良好になった可能性もある。「テレビと同じだ」と思いこんで再生していない方は、ぜひ確かめてほしい。近年では音ネガの波形からデジタルで音を復元する技術も導入されつつあり、一方で磁気素材は地磁気の影響や風化で年々劣化するため、必ずしもどちらが良いとは言えない状況となっている。なお「ウルトラマン」「ウルトラセブン」は放送に近い時期に発売された「ドラマ編」のLPレコードがあり、これは磁気素材のクリアな音源を使用している。
【2003年9月7日脱稿】初出:「宇宙船」(朝日ソノラマ)