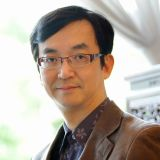※2002年12月10日発売号の原稿です。
●“良い子”は本当に良いのか?
“良い子”が増えたと言われます。私も学生時代には「戦後教育の“良い子”で育てられたような」と評されたので、今に限ったことではないでしょうが。
ここで言う“良い子”というのは、法律や校則などルールを守って、親や先生の言うことを聞き……みたいな人間を指します。それの何が悪いの? と言われると、いや悪くはないでしょう。まったく法律を犯さずに一生を過ごすことができれば、経歴的には……。特に今は社会が成熟してきて、できないことやルールから逸脱したことに対して減点法的に評価される傾向が強いですから、なおのことでしょう。
でも、「悪いことをしない」ということは本当に良し悪しの基準になるのでしょうか? それを「良い」と人の評価を直結させてしまうのは、どうなのでしょうか? 「悪い」の否定が「良い」となると思ってしまうのは、デジタル的な論理の落とし穴であり錯覚です。一見間違ってはいないだけに、よけいにややこしい事態を招いているようにも思います。
本当は、良いひとと評価されることの必要条件にルール違反しないことが含まれているだけのことです。ちょっと考えれば、「ルール違反しないことが良い評価に直結する」ことはあり得ないのがわかると思います。論理学でも、そんな誤解の落とし穴を防ぐために必要条件・十分条件や対偶みたいなもので整理しているわけで、そこを無視して「悪いの反対は良い」みたいに都合のよいとこだけを抜き出してことを運ぶのは、小学生の理屈みたいでどうかなと思います。
ルールって何だろう? それを守っているだけで良いのか? そういうことを考えるとき、思い浮かぶのは『戦闘メカ ザブングル』(1982年)というアニメ作品です。
●掟破りのザブングル
この作品は富野由悠季原作・監督(原作は鈴木良武と共同)のロボットアニメで、サンライズによって1年間のアニメとして製作され、1983年には再編集による劇場版『ザブングルグラフィティ』が公開されたほどの人気作でした。現在でも富野監督は、閉塞した社会の枠から脱出していこうとする人びとがシベリアの原野で活発な生活を送るさまを描いた新作TVアニメ『オーバーマン キングゲイナー』を発表中ですが、『ザブングル』もまた似たような型破りな部分が満載の作品でした。
──惑星ゾラと呼ばれている地球。ほとんどが砂漠化した原野の中で、一般人はシビリアンと呼ばれ、ウォーカーマシンなる二足歩行のマシンを使ってアメリカ開拓時代にも似た社会をつくっていた。ドーム都市に住むイノセントを自称する人びとは、シビリアンから鉱石ブルーストーンを上納させ、統治を行っていた。
シビリアン社会のルールは単純だ。どんなに悪いことをしても三日間逃げ切ればOK、罪には問われない。だが、ここに親を殺されて三日が過ぎても仇討ちを忘れない少年がいた。彼の名はジロン・アモス。その執念は、最初こそ笑われていたものの、やがて周囲を巻き込んで大いなる時代の変革へとつながっていく……。
だいたいこういう背景に、ジロンが荒野を走って走って走りぬくその活力ある映像が物語を引っぱっていった作品です。とかく放映中は、「掟破り」「パターン破り」と呼ばれることの多かった作品でもあります。
●ルールとは何のためにあるのか?
とかく三日の間に仇討ちできなかったのは、お前の方が悪い……と、新しく仲間になったサンドラットの面々からもアイアン・ギアーのクルーからもジロンは言われ、ボコボコに批判されますが、ともかくジロンは納得しなません。この頑迷とも取れるこだわりが、物語の発端部分を引っぱっていきます。理屈をこね回すわけでもなく、あの手この手でジロンが動いていく中で、ほとんど失敗したり、裏目に出たりするのに、めげずに肉迫していく。このアクションを基本にして引っぱっていく姿勢に好感が持てます。
そして彼の執念と行動にハラハラドキドキする中で、彼を縛っている「三日間の掟」の正体とは何なのか、そもそも社会を律するルールとは何かという疑問も密かに浮き彫りになっていきます。それは結局、惑星ゾラの話ではないわけです。普段、われわれも無意識のうちにそういうルールにいかに強制されているかという困った事実があるから、それがカリカチュアされているわけです。
“惑星ゾラ”というのはどこか?、というのは、設定中心主義の作品だと物語の中心におかれる“謎”になりそうです。でも、これは遠未来の地球で、それ自体は非常によくある話なのですが、これにしても最初からナレーションが「惑星ゾラと呼ばれている地球」と言っていたりして、あまりにもあからさまなので気づかなかったりする皮肉がこめられています。富野監督の前作『伝説巨神イデオン』で、「異星人と言えども母なる大地を意味する惑星のことは“地球”と呼ぶだろう」ということが展開されただけに、よけいに引っかけが大きくなったとも言えますが。
ともかく、それぐらい人間の思考や習慣の中にルールというのは固定観念とセットで忍び込み、生活を楽にする一方で、縛りつけているものなのです。
●究極の復讐話?
ジロンの場合、彼を縛っているルールは、ジロンの持つ復讐心によって破壊されていきます。結局、1年間の物語の全貌をシンプル化すると、ジロンが破壊し尽くした従来の秩序の後に、新しい秩序が生まれつつあった、ということになるでしょう。
しかし、ジロンがルール破壊をしまくった犯罪王かというと、まったくそんなことはありません。むしろ彼の情熱と、やや軽率なところがあっても憎めないようなところこそが印象に残るのではないでしょうか。それゆえ、ジロンが親の仇ティンプを討ち、本懐を遂げる(と見えた)シーンでは、けっこう盛り上がって思わずもらい泣き、みたいになるはずです。
こういったルール破壊と人情の間にある落差と相関が非常に大事なポイントです。
復讐というのは、「お話」の誕生とともにあるくらい、人間にとっては非常に基本的で根元的な動機となるものです。いつも年の瀬が近づくと『赤穂浪士』をやっているのが何よりの証拠です。ですが、一方で仇討ちを縛るルールも必ずあるわけで(赤穂浪士は切腹させられている)、根元的であるがゆえの秩序崩壊という要素も強い、結果ルールに締め付けられる部分も大きいものです。
それを考えると、ルールの方までひっくり返していくジロンのパワーの圧巻さが実感できますし、しかもドロドロといつまでも復讐心を引きずるわけでもなく、ルールの方を一方的に悪と決めつけるでもなく、行動の果てに結果として世の方が変わっていくだろうというあたりが、さわやかで雄大です。そういう形で彼の復讐が完結したと見れば、なかなか類を見ない究極の復讐譚だったとも言えるのではないでしょうか。
●ルールという枠組を突破するために
「ルールとは破壊されるためにある」というようなレトリック(修辞)は、こういうことを表現するためにこそあるわけです。くれぐれも気をつけて欲しいのは「自分が正当だと思えば、ルールをいくら破壊しても良い」などと言おうとしているのではないということですね。「ルールは守った方が良い、だけど……」という、この「……」の部分にこそ本質的な意味があるということです。
ジロンが仇討ちを続けようと思ったきっかけには、もちろん悔しいという感情もありますが、彼を縛っていた三日間のルールという存在も大きいのではないでしょうか。ルールで縛られることによって、悔しさのサイズが測られたと言っても良いでしょう。それはとりもなおさずジロンが親から受けた愛情や恩義のサイズや深さを測るものでもあるわけです。
「三日の掟」の存在理由とは、怨恨を抱いて生きていくと、仇討ちされた側にもまた新たな怨恨が発生、無限連鎖が続く、そのフェイル・セイフなわけです。荒れて再生を待っている大地には殺し合いを受け入れる余裕はない。トータルサイズの縮んだ世界では、振り返るよりは忘れて前を見て生きた方が良い。いろいろあるのでしょう。容易に想像できます。
だが、そんな秩序もルールも破壊されるべきときには破壊された方が良いに決まってます。破壊されるまでがルールの賞味期限だった……そんな実例はいくらでもあると思います。だから、ルールに従うこと自体に意味はないのです。なぜルールが必要なのか、何を縛りどう整理しようとしているのか、結果何がお得になってトレードオフになって損することとは何か。それを考える目安になることにこそ意味があるわけです。
ルールに従って生きていれば“良い子”になるなら、この世で一番の良い子はプログラムに忠実なロボットになってしまいますよね。むしろ脱ルールも可能なくらい知恵があり、かつ元気いっぱいに動ける子こそが、本当の“良い子”なのではないでしょうか。
【2002年11月28日脱稿】初出:「月刊アニメージュ」(徳間書店)