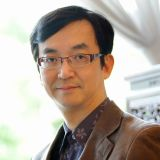●ガンダムのイントロふたたび
前回のガンダム冒頭の音の話は、ちょっと駆け足で説明不足だった反省があるので、もう少し補足してお話しておきましょう。何バージョンもある冒頭の映像と音の関係の差、どこを注目ポイントとすれば良いか、っていうことを整理します。
まずオリジナル中のオリジナル、テレビ版では、開巻いきなり人工の大地がフカンで映り、ゆっくりと移動が始まります。そして鳥がフレームインし、消えるように小さくなっていく。移動がゆるやかになると、いきなり大地をメガ粒子砲のビームが貫きます(カット1)。するとカメラは外の宇宙空間に出て、ムサイ艦隊の一斉射撃を描写し、ビームの原因を見せます(カット2)。そして、ようやくスペースコロニー全景が出ます。外壁に巻き起こる大爆発で、艦隊の砲撃していたものが円筒形のコロニーであること、カット1の貫かれた大地はその円筒の内壁だったらしいことが示され、タイプの違う戦艦がフレームインして爆発することで、それが戦争によることが判ります(カット3)。
ファースト・ガンダムのイントロは、このわずか3カットの構成で、宇宙移民の時代とそこで起きた戦争状態を描写しているわけです。
まずは、松浦典良音響監督によるテレビ版の音づくりを掘り下げてみましょう。冒頭からカット1の爆発までは、荘厳な音楽とナレーションのみ。効果音は一切ありません。画面もフカンであるため、臨場感はなく、鳥さえも無音で飛ぶので記録フィルムを観ているようなテイストです。それが、ビームの爆発音で一転して観客は戦場にたたき込まれる。この「一転」という感触、伝説の世界にいたのが厳しい現実にたたき込まれたかのような部分が、物語のイントロダクションとして大きな役割を果たしている感があります。
最初のカット1は宇宙空間とは判らない普通の大地としか見えない画面なのに、実は宇宙空間に浮かんだ大地だった! 画面では地面にいきなり火柱が上がったとしか見えないのが、実は外から戦艦にビーム砲を撃ち込まれたのだ! という、この驚き感が、無音と現実音を爆発の音で境界づけることで、うまく表現されているわけです。
●劇場版のイントロ音響
劇場版ではどうでしょうか。劇場化にあたっては、カット1の手前にカット0とでも呼ぶべき新作映像が追加になっています。それはスペースコロニーの全景で、外側から内部の人工の大地が見える構図になっています。ナレーションも、テレビ版の叙事詩的な響きがするものから、「数百基の巨大なスペースコロニーが」とか「円筒の内壁を人工の大地とし」などなど、具体的な説明要素が増えています。
第1作目は松浦音響監督によるもので、テレビ版の音響設計と基本は同じです。第2作目「哀戦士編」と第3作目「めぐりあい宇宙(そら)編」は、浦上靖夫監督が担当。肩書きも「オーディオディレクター」に変わっています。浦上監督は、このテレビ版でも最初の1クールに反復されておなじみのイントロに、まったく別の音をつけました。
宇宙空間からのスペースコロニー、カット0の頭には、荘厳で厚みのある序曲のかわりに、音楽とも言い難いチェロのシンプルな音色が響き、それが逆に静かな拡がりを感じさせてくれます。鳥のフレームインには遠く響く鳴き声がつき、ビーム爆発の直前には接近音が入るようになりました。
その分、どういう効果になっているでしょうか? 音楽よりも、効果音が浮き立つようになったことで、映像とともにいるという感覚があり、そして外壁側から何か音が迫ってくることで恐怖感が生まれたのではないでしょうか。
テレビ版と1作目がドキュメンタリーフィルム風の隔絶した感じがあったとすると、2作目、3作目は同じ映像が流れながらも、その現場にいて宇宙世紀の惨劇を見つめているという「視線」が追加された感があるようです。ただし、それはまだ「神の目」に近いものだったと思います。
●さて、特別版DVDでは?
これが5.1ch化DVDの「特別版」になると、また3本が3本とも違った音づくりがなされていて、実に面白いです。
1作目は『∀ガンダム』の鶴岡陽太音響監督によるもの。いちばん驚いたことは、カット0のさらに手前から効果音がついていることでした。手前とはなにか? それは、サンライズのクレジット映像なんですね(笑)。つまり本編の始まる前、カット・マイナス1から、音のドラマはスタートしていることになります。5.1chの音場の臨場感は格段に上がるため、映像以上に連続性が強く、観客をなじませ、早く音の世界に引き込むためにスタートポイントすらも変える必要があった、ということではないでしょうか。
マイナス・ポイントから聞こえ出す音とは何か? それは空気というか、風のような音です。カット0でコロニーの映像がスタートすると、サブ・ウーハーから「ドーーーン」という重々しい出現音のような音が響き、おなじみのナレーションが始まります。地面をなめるショットでは高空に流れる風、そして遠い音で鳥の鳴き声が入り、爆発に続きます。接近音があるのは変わりませんが、その手前にも予兆のような「ドーン」と出現音が入っているのが特徴です。音楽についてはカット4になるまで入ってなく、観客の意識を音の場の力で宇宙世紀の世界に巻き込むような感じが強くあります。つまり、臨場感はさらに上がって、「神の目」から、まるで自分たちがコロニー生活者になっったかのような「人間の視点」になっているのです。
2作目になると、音響監督は『BLOOD THE LAST VAMPIRE』の百瀬慶一氏となり、またも驚きの音響が提示されます。同様にサンライズマークから効果音がスタートするのですが、その音が違うのです。それは空気の音ではなく、重低音を響かせた機械の音です。さらに、コロニー全景をなめるショットでは、異常なことが起きます。本来はナレーションが入ることを前提としたものにも関わらず、音楽もナレーション音声もいっさい入らずに、約20秒という長い時間にわたってコロニーの全景映像とこの重機械音だけが流れるのです。観客の気持ち的には思わずコロニーの隙間から見える大地に気持ちが入っていく……と、カットが切り替わり、その大地のフカンになって、そこからナレーションが始まるのです。
リアルに考えたら、宇宙空間でコロニーのシリンダーを回転させるモーター音なんぞは聞こえるわけがないのですが(笑)、凄い臨場感です。こんなに何度も観たフィルムなのに、音の設計の変更だけで、宇宙空間に巨大な物体がある、というコロニーの存在感が浮き立ち、まったく違った印象になりました。まるで今まで気づかなかったコロニーという登場キャラクターが自己主張を始めたようにすら実感しました。
これが音響の力なのです。
では、3作目はいったいどうなってしまうのか? これは……なぜか劇場公開時のものに非常に近しいものなんです。冒頭だけでなく、全編の音楽設計も……。3作目だけは音楽が溜め録りではなく、フィルムに合わせて作曲されたという事情も関係しているのかもしれません。というので、もし3作目しか持っていなくて「あまり変わっていないな」と思っておられたら、ぜひ1作目と2作目も検証してみて欲しいですよね。
せっかく音響が変わったんだから、変わったことを楽しむ、というのはこういうことなんだと思いますから……。
ガンダム世界では、21世紀の嬉しい贈り物として、安彦良和さんのファーストガンダムの漫画もスタートしました。無音のガンダム漫画に、果たして皆さんはどのような音響をつけて読んでおられるのでしょうか? たったひとつのフィルムでも、人によってこれだけ多様な音の解釈ができるのですから、可能性は無限大。やっぱりアニメはそういうところが面白いんですね。
というあたりで、続きはまた次号です。
【2001年7月24日脱稿】初出:「月刊アニメージュ」(徳間書店)