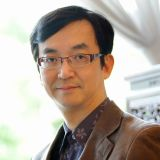《前説》
原稿を書きながら朝の『仮面ライダーアギト』を観ていたら、映画館内での会話がありました。かかっていたフィルムは、なんとビックリ『白蛇伝』! そう、東映動画(現:東映アニメーション)の長編アニメ映画第1作です。同じ東映作品ならではのチョイスですが、渋いですねー。先日亡くなった相米慎二監督の『翔んだカップル』で画面の片隅に「冷たい方程式」と学園祭の告知があったみたいなオドロキがありました。うーん、変なたとえかな。
●『鉄腕アトム』の音世界
さて、音の話を続けてきて6回目。そろそろ一段落といきましょう。今回は原点を探ってみましょう。まずは「効果音・イコール・キャラクター」という原点。
前回は最初の『ルパン三世』の音の話でした。この作品、第3話から「サウンド/大野松雄」とクレジットされています。大野松雄と言えば電子音楽の草分けにして、日本最初の30分TVシリーズのアニメ『鉄腕アトム』の音響構成を担当した方として有名です。
アトムの放映は1963年──1975年になってその効果音集は「鉄腕アトム 音の世界」というアルバムにまとめられました。1998年にワーナー・ミュージック・ジャパンからCD化もされています。日本初のテレビアニメヒーロー、アトムの最大の特徴とはなにか? それは実は「音」だった、ということがよく判るアルバムです。
『鉄腕アトム』は1980年にも手塚治虫自身の手でリメイクされています。カラー化され、作画技術も向上して旧作に比べればずっと原作に似た絵柄にも関わらず、放映が始まるなり、漠然とした違和感を覚えました。それは、アトムが歩いたときに、あの聞き慣れた「チュッ、ピッ、チュッ、ピッ……」という足音がしなかったからです。
それぐらいアトムの足音とキャラクターは知らず知らずのうちに頭の中で一体化していたのです。ロボットだったら機械的な足音でも良さそうなものですが、アトムの足音は高く電子的に響いて未来的で、可愛いいところがよく似合っていました。
もちろん原作漫画には、よほどのことがない限りアトムの足音の擬音は描かれていないわけですが(いちいち描いていたらうるさくて読めたものではない)、アトムはきっとこういう足音で歩いている──という雰囲気ごと原作を補完するようにアニメ版の効果音が作用していたわけですね。いつしか原作を読むときにも、あの足音をつけるようになっていたのかもしれません。
筆者が「アニメの効果音」を明確に意識したのも、思い起こせば実はこのアトムの足音が最初でした。放映当時は小学生低学年だったわけですが、帯がシールになっている光文社のカッパ・コミックスの中にアトムの裏話的な記事が掲載されて、そこで効果音のことについて述べられたのを食い入るように読んだことを思い出します。
あの未来的で電子的、子ども心にも不思議だったSF的足音はどうやってつくられたか? それは実は「マリンバの音」だったというのです。
●手作業と電子音の複合効果
つまり、マリンバで演奏した連続音をオープンリール式のテープレコーダーにかけて、リールの回転を指で止めたり動かしたりして加工したのだというのです。すると、回転数がふわっと速くなるわけで、その回転数の立ち上がりのところが周波数の変動になって、ああいう微妙にうねった音になる、ということなのでした。いま聞き直すと、それにエコー等で電子的な後加工もしてあるようですが。
大野松雄は現代音楽、それも電子楽器によるものを開拓した人物ですが、すべてを電気まかせにしていたわけではない、というところが面白いです。この時代だと、電子音といっても、簡単な帰還回路による発振(マイクをスピーカーに近づけたときの「ピー」というハウリング音と同じ原理)とエコーぐらいしかなかったでしょう。だから、音に変化をつけるときにテープレコーダーの回転数をいじったり逆回転したりして加工するというのは、基本的な技法だったようです。
ということは、アトムの足音にしても、足音のデータが先にあって、それをはめこんだということではなくて、「アトムなら、誰でもこういう足音がすると思うに違いない」というイメージと、いろんな素材を加工して聞こえてくる音をマッチングさせながら、無からつくりあげていった──と言えるのではないでしょうか。そのデリケートなすり合わせに、職人芸的な手作業が欠かせない、ということだったと思うのです。
しかも、そこに音楽家のセンスが加わったことで、また一段と生命の息吹を感じる音づくりとなっていた──だからこそ印象に残って、何年たっても忘れられない息吹をキャラクターにもたらしたわけです。セル画のコマ撮りだけではなく、こういったことも「生命を吹き込む」アニメーションなのではないか、とデジタルでいろんなことができるいまだから、逆に肉体感覚の大切さを痛切に思い知らされます。
「鉄腕アトム 音の世界」は、その他にも懐かしの「これぞアトム」という音が目白押しの傑作アルバムです。口真似(文字真似)すると、こんな感じだったりして──。
・怪人のアクセント「キシーーーン! シャンシャンシャン……」
・ピーチクパーチク「チュクーウィーチック、チュクーウィーチック」
・アトム、サーチライト「シュボッ!」
・アトム対怪人「ボン、ベン、ビン!」(ド・レ・ミの節で)
シンセ的電子音でもなく自然音でもない、極めて漫画のオノマトペ(擬音)に近い音は、人間的でありながら抽象度が高く、いま聞き直すと本当に新鮮ですね。
●世界観を描く効果音
さて、もうひとつ。「効果音・イコール・世界観」という原点を挙げましょう。シンセサイザーが楽器として立ち上がってきた時期、ユニークなアニメ効果音が現れました。1974年の『宇宙戦艦ヤマト』です。
後にアニメブームを起こしたこの作品、もちろん他にも斬新な部分はたくさんあったわけですが、柏原満の効果音もそのSF的世界観の確立に大きな役割を果たしていると思います。この作品も、効果音を立て役者としたアルバムが出ています。1996年に日本コロムビアから発売された「サウンド・ファンタジア・シリーズ●宇宙戦艦ヤマト」です。
2枚組のこのアルバム、パート1から完結編までの代表的な音楽に柏原満の効果音を重ねたものです。オープニングは、すでに生涯百万回ぐらい耳にした交響組曲のイントロから川島和子のスキャットに移る定番の構成をとっているんですが、ここで「シュルルルルルル ドヒュリリュウウゥ……」と聞いただけでイッパツで遊星爆弾と判る効果音がかぶる──そうするともう眼前には第1話の赤い地球の映像がひろがって、もう涙ナミダです。
島大介がコンソールを操作してエンジン出力が変化する音がするだけで、ヤマト発進と判ったりして、ワクワクしてきます。武器の音も、「ドバシュ! ウリュウリュウリュウリュ」(ショックカノンだね)「ビニョ~ン ヅゥウウウーーーン ヅゥウウウーーーン」(七色星団、ワープ光線の音だ!)「ケション!」(煙突ミサイル発射!)と、ほとんど何が行われているのか音だけで完璧に映像ごと思い出せたりして。カセットテープにテレビから録音して何度も耳に染みつくまで聴いた世代には、もうたまらない効果音が、宮川泰の音楽にのせて続々登場。かつては「ああ、音楽だけで聴きたい!」と思ったものですが、いまとなってはこの効果音含めたものの方が魂のふるさとと感じられるのだから、不思議なもんです。
フィルムを思い起こせば、第1話冒頭、宇宙空間をトラックバックする長回しのシーンに、無限の拡がりと神秘を感じさせる宇宙音がよりそっていたり、地球側とガミラス側で宇宙船のエンジン音や光線砲の音が微妙に違っていたりで、イントロから観客を引き込むのに効果音が大きく作用していた──そんな記憶もよみがえります。有名な波動砲発射の効果音シークエンスも、艦内の電源を落としてエネルギーを蓄える設定シチュエーションには効果音が大きな役目を果たしていました。エネルギーを「ギュッギュッギュッギュッ……」と、いかにも圧縮しているという感じの音に続いて機械音が何重かに重ねられてプロセスが展開する。こんな風に効果音がSF設定と背後にある世界観を表現したわけですね。発射の瞬間の「ピシャーーオワッ!」って音は、他作品によく流用されていて、『ドラえもん』でも雷になると「波動砲発射!」と思っちゃたりもしますが(笑)。
このように、効果音もアニメ作品独自のSF的世界観を確立するのに大きな役割を果たすことができる、それがヤマトの魅力の大きなパートを占めていた、ということが確認できるアルバムでした。
こちらの聞き込みや、思い入れが足りないのかもしれませんが、こんな風にキャラクターや世界観を感じて、思わず宴会で口まねをしたくなるような効果音に、また出会いたいですね。では、音の話はこれにて。来月、また別のテーマでお会いしましょう(敬称略)。
《付記》その後取材を重ねて「アトム」と「ヤマト」の効果音の関係や柏原満さんとも知己を得て、その仕事に関する研究も進んでいます。いろいろ修正したいとこですが、とりあえず掲載時のままで。柏原満さんのお仕事は、それほど遠くない時期にお見せできるものがあると思います。
【2001年10月28日脱稿】初出:「月刊アニメージュ」(徳間書店)