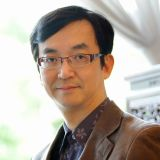●『未来少年コナン』のキャラクター描写
今回も続けて音の話をいたしましょう。前回は、音の付け方と世界観の関係のようなものについて書きました。今回は、音がときにキャラクターの性格から存在感まで、大きく変えてしまうという事例について取り上げてみたいと思います。
ひとつのフィルムに複数の音がついているもうひとつの事例として、今回は『未来少年コナン』のテレビ版と映画版を比較してみましょう。『未来少年コナン』(コナンと略すと最近では名探偵になる)は、宮崎駿の事実上の監督デビュー作です。クレジット上では「演出」となっていて、立場としてはチーフ・ディレクター、つまり総監督です。児童文学の原作ものですが、かなりの部分が宮崎監督によるオリジナルの作品です。9月からDVDが低価格版として再びリリースされますが、再見して驚くのは人物を深く掘り下げた描写力です。どの登場人物も、必ず一面的ではない描き方がなされ、しかも展開や人間関係の変化で実に様々な面が見えてくるという、それだけでも見応えのある作品です。
たとえば主人公コナンが、どんな困難になっても意外な力を発揮してそれを乗り切ってしまうことはよく知られています。コナンの活躍は、鉄をも曲げる怪力や、高いところから落下したり、巨大な岩を動かしたり、果ては足指で飛行機の翼にぶら下がったりするような、ずばぬけて強力な肉体パワーの発揮として描かれているから印象に残ります。
しかし、コナンはただ力が強いだけの少年として描かれているわけではありません。そこに気づくと楽しさ倍増です。彼が力を発揮するのは、何が何でも行動しなければという強い思いに突き動かされたときなのです。育ての親と2人きりだっために人との接し方が未熟で口数も少ないので判りにくいのですが、非常に強い精神力と、なすべきことに対して正しい考え方を思っています。それが行動として現れたときに、現実では困難な状況突破をするときに先のようなスーパーパワーを出すように描かれているということです。
だから、彼が怪力を発するシーンだけを集めたとしても、それは何か違うものになってしまう……そういう深い演出が成されているのが宮崎監督のテレビ版コナンです。
●映画化で一新されたコナンの音
さて、映画化された『未来少年コナン』です。映画版では実写映画の佐藤肇監督がテレビ版のフィルムだけを使って再編集を手がけました。もともと2時間前後にまとめるのは誰が担当しても非常に困難なストーリーだと思います。
それよりも個人的にまずショックだったのは、音楽も効果音も一切が変更になっていたことです。テレビ版では登場人物は「マンガ」的ではなく、機械文明と言っても謎の動力エンジンや怪光線は登場せず、重油と火薬が基本の世界で、音もそういうものがベースだったはずが「こ、こうなってしまうのか?」という驚きがありました。
まず、コナンがラナと初めて会話をするシーン。ここでコナンは気持ちが通じるにしたがっておどけて逆立ちをしているのですが、ここで手や足をつくたびに「ピッ、ポコッ」と妙なギャグ音が入っているのです。「鉄腕アトムが歩いているんじゃないんだから」と思わずスクリーンにツッコミ入れたくなります。コナンは怪力ロボットではありません。
笑えるのがインダストリアのクズウの持っているマシンガン。おじいを殺す原因ともなった最初の発砲シーンでは、「キシーン、ピュルルルルル!」……ひえー、これは聞き慣れたガミラス艦(宇宙戦艦ヤマト)の光線砲の音じゃないですか! しかも、同じクズウが港でコナンを追撃するときには、同じ銃なのにマシンガンの音がついている(笑)。さらに窓にへばりついたコナンを威嚇するときには、また同じ銃が光線銃の音に(笑)。ラナがへばりついてマガジンを奪い取ると、光線銃のはずなのに弾丸がボロボロと落ちる(笑)。えーい、この銃は弾を出すのか光線を出すのか、いったいどっちじゃ? と思わず頭がグラグラしちゃいます。バラクーダ号を追撃するガンボートも、宮崎監督らしい丸っこいデザインで、ちょっと古くさい感じが良いんですが、これが大砲を射撃すると「ビコー、ビコー!」 あ、これはアルカディア号(宇宙海賊キャプテンハーロック)の主砲と同じ音……。そういうSF戦闘アニメではないんですが。
まあ作画はテレビと同じだから、それを楽しめば良いか(マニアの発想)と割り切ろうと思ったら、こんな調子でどうにも音だけで実に居心地の悪い思いをしたということです。
●音が変われば人格も変わる
さて本題。特に驚いたのは、音によって重要な登場人物の性格というか、人格が全く変わってしまったシーンがあったことです。これは前代未聞の出来事でした。
『未来少年コナン』の世界では、超磁力兵器によって人類は絶滅の危機に瀕し大陸は海没、生き残った人々は機械文明を信奉するインダストリアと、自然と調和して生きるハイハーバーとに分かれて暮らしています(宮崎アニメの基本ですね)。インダストリアのレプカは、三角塔の太陽エネルギーを復活させて武力による世界の支配をひそかに野心として抱き、エネルギー復活のカギを握るラオ博士を拘束し、孫娘のラナを人質にして脅迫しようとしています。
テレビ版では第22話で、レプカが捕らえベッドの上に縛り付けたラオ博士に協力を強要すると、博士は当然拒否の回答をします。実はこれが伏線になっています。レプカの卑劣な策略でラナがその前に連れて来られると、博士はラナを認識せずに、レプカに向かって語ったのとまったく同じ協力拒否の言葉を繰り返すのです。そこでラナは博士が恐らくは拷問のため視力も聴力も失ってしまったことに気づくわけです。ここではラナは悲しみを乗り越え、心はいっそう毅然とし、堂々とレプカに刃向かうというところが実に感動的な、テンション高いシーンなんですね。
このときのレプカの反応がみものです。確かにそれほどまでに激しい拷問を加えたのはレプカですが、さすがに「まずい……やり過ぎたか」と思ったのか、博士とラナがテレパシーの会話に入ると、あわてて本当に目が見えないのかどうか確認しようとするんですね。開いた目の前に拳を突き出したりして……まばたきをするかどうかで確かめるんです。手のひらを左右にふったりもします。逆らう人を恐喝したり殺害したりで非道の限りを尽くしているレプカですが、彼もまた追いつめられた者なのです。さすがにここで博士の身を確認するという描写が、いかにもに宮崎監督らしい重層的な人間描写です。
映画版でもほぼ同じシーンがクライマックスとして盛り込まれています。やはりラナに博士の視力聴力のことを指摘されたレプカは、作画はテレビと同じなので、同じ芝居をします。同じように博士の前にレプカが拳を突き出すと……。
「バシッ!」
え? え?
この拳を出す絵は寸止めのはずだけど、も、もしかして殴った音が……入っている??
これではレプカは、あまりに非人間的な男になってしまいます。縛り付けた人間、しかも自分の拷問で視力を失った老人に「正拳づき!」ですから。しかも、テレビで感じた重層的な厚みはどこへやら、です。
このように、たったひとつの効果音が、何もかもぶち壊すということがあり得るわけです。テレビでは破綻ないよう細心の注意をもってプロットから構図から作画から、トータルの積み上げで描かれていた人間像も、効果音ひとつで瓦解し、まったくの別人格が出現してしまうわけです。
音って、こういう力を持っているんです。
アニメで人間を描くには、設定も必要ですし、脚本も作画も声演も、何もかもみな大事なものです。でも、音に関してはあまりにも自然に溶け込むのように作りこまれているがゆえに、意外とあまり意識されていない実情があるのでないでしょうか。音のあり方次第ですべて変わるかもしれない、ということを意識しながらアニメ見るのも、面白いことではないでしょうか。
蛇足ですが映画版の『未来少年コナン』は、ラオ博士が世界を回って人々を救うぞと、コナンたちに別れを告げるところで終わり、なんです。レプカとともに大爆発したはずのフライングマシンに乗って(笑)。目も耳も不自由になったはずのラオ博士が(笑)。
【2001年8月27日脱稿】初出:「月刊アニメージュ」(徳間書店)