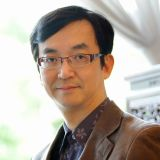※2003年2月10日発売号の原稿です。
《前説》
非常に充実した仕事をさせていただきました。「無敵超人ザンボット3&無敵鋼人ダイターン3総音楽集」(キングレコード2003/2/26発売)です。旧作のBGM集で、もちろん全楽曲を収録することも大きな目的でしたが、いかにそれを充実した「商品」に仕上げていくか、頭を使いました。基本思想は“自分がお客だったら飛びあがって喜ぶもの”。当然のことではありますが、それを再認識させられました。お楽しみに。
●生涯にもっとも多く回数観た作品
もし特別に好きなアニメ作品ができたとして、普通はどれくらいの回数を反復するものでしょうか?
私自身の場合は昔から名画座に通い、ビデオを録画し、ビデオグラムをよく買ったりしてきたわりには、意外に作品を見返すことの少ない方じゃないかと思ったりします。そんな中でも、十回を越えて観た作品というと、さらに少なくなってしまうかも。
これまでの生涯でもっとも数多く楽しんだアニメ作品というと、尺の短いものでは間違いなく『銀河旋風ブライガー』のオープニングです。金田伊功によるロボットアクションのエッセンスが濃密に詰まった一種の短編です。これは本放送当時、百回以上は再生しましたから、間違いなく一位でしょう。
そしてTVアニメ本編の中で、これまで一番数多く観たのではないかと思われるのが、今回取り上げる『マグネロボ ガ・キーン』第1話「無敵の王者ガ・キーン」(脚本・山浦弘靖、演出・勝間田具治)です。これまでも機会あれば取り上げたかった作品ですが、アニメ用オリジナルのため原作漫画が読めるわけでもなく、ビデオグラム化のチャンスもなくということで、泣く泣く見送った作品でもあります。
今回、晴れてDVDボックスとなっての発売。いや、長らく待ちわびました。
この第1話こそは、「究極のロボットアニメ」とでも言うべき位置にある偉大なフィルム。まさにロボットアニメを語るに欠かせない作品なのです。
●驚くべきロボットアニメ的要素の濃さ
『ガ・キーン』第1話最大の魅力とは、今観ても驚くほどの「濃密さ」です。
それも単に消化すべきことを並べ、駆け足でまくしたてたという風ではなく、熟練スタッフの「熟練した技」を感じられるところにポイントがあります。独特の呼吸のような緩急・リズムも感じられ、その中でスーパーロボットの自分が好きな要素が鮮やかに繰り広げられ、何度見ても心地よさを感じるフィルムです。
物語自体は非常に古典的な導入篇と言えます。
──イザール星人は二百万年前に地球を訪れた異星人だが、侵略に失敗して地底に潜み反撃の機会を待っていた。世界各地に拡がる異変から、その目覚めを予見した地球システム研究所の花月博士は、移動要塞ゴッドフリーダムを完成。無敵のロボット、ガ・キーンとともにイザール星人の合成獣に立ち向かう……。
ここだけ取り出すと、他作品とあまり変わることはありません。ですが、そのプロセスの中で出てくるものが、ひとつひとつに目新しくはなくとも、洗練されたものとして現れた上に、これでもかというぐらい多重化されて眼前に繰り出されていくところが、ひとつの「濃密さ」につながっていく部分です。
第1話とは導入の役目を背負ったものですから、一般的にはいろんなことを紹介するだけで手一杯になりがちです。世界観、登場人物個別の性格、人間関係、敵味方の設定などなど……こういったどんなドラマにも要求されるイントロダクションに加えて、ロボットアニメでは、玩具と連携した「変形・合体」といったファクターが重要です。これに時間をかけてたっぷりと見せ場をつくり、なおかつ敵を倒してすかっとカタルシスを発生させ、子供たちい「来週も見よう」という気にさせなければならないわけです。
ロボットアニメの第1話とは、なんとも大変な宿命を背負っているわけですね。
●ロボット的要素を何倍にも重ねた密度感
なので、よくよく考えてみると、かなりの作品がどこかしら基本要素を第1話から削って、「追って紹介」としがちであるのに気づきます。例えば『マジンガーZ』にしても第1話では敵を倒していませんし、初合体が第2話、第3話へと繰り延べになっている作品も少なくないはずです。
ところが、『ガ・キーン』第1話ではわずか25分の番組枠(キー局では本放送版エンディング無しのフォーマット)の中で、これを全部展開してみせたことが凄い。いや、ものによっては何倍にも要素を増やして見せているのに感動します。
一例として、ロボットが合体して完成するまでの流れ、いわゆる“ワンダバ”と呼ばれ、毎週繰り返されることになるプロセスに注目してみましょう。まず発進時には、男性主人公の北条猛と女性主人公の花月舞がプラス・マグネマン、マイナス・マグネマンに変身。スピリット・エンジェル号という小型メカに乗って発進口を急スピードでくぐりぬけ、ゴッドフリーダムから出たところで二機に分離。別途射出されたプライザーとマイティにそれぞれ合体します。
変身→メカ搭乗→発進→合体と、ガ・キーン本体に到達する前に、要素はてんこ盛り。渡辺宙明の軽快な音楽に乗せ、いちいちかけ声も勇ましく鮮やかな段取りを追っていくだけでも興奮します。小型ロボにも様々な武器があり、それを見せたところで真打ちの登場。ここで、男女ロボットを飛び出た猛と舞が「スイート・クロス!」のかけ声とともにガ・キーンのシンボルに変形。それを中心にして、射出されたパーツが球体関節の力を得て、ガ・キーンに合体!
さらに第1話では、敵の合成獣が二体登場! ガ・キーンは一度分離したプライザーとマイティを呼び寄せ、両腕のコンビネーションをチェンジ、必殺技の「ガ・キーンフルパワー」で敵を仕留めます。
このめまぐるしいほど大量のメカアクション要素を十分もない尺の中で見せていくわけです。
他の部分も濃いです。自らの限界へ挑戦しようと父に反発する主人公・猛の闘志、舞の愛らしさと変身後の凛々しさの対比といったキャラクターの強い印象づけ、ロボットの足がめり込んで地面がめくれ上がる重量感、身長差の大きな敵怪獣に向かって手足のナイフで切りかかり、相手の体重を応用してのバックブリーカーという前代未聞、階級差のあるロボット格闘アクション(友永和秀による重量感あふれる作画が迫力倍加!)、おまけに父の道場で息継ぎ的に風鈴の音が静かに鳴ってみたり、ライバル的キャラと初対面でいきなり殴りあったり、ラストは父子で同じ夕陽を見るというドラマ展開もきちんとやっていたりして。メカアクションとドラマが好対照のアクセントとなり、全体の圧縮感、密度感が良い味に仕上がっていくわけです。
まさに、究極のロボットアニメ的感動とはこういったものでしょう。
●洗練されたロボットセンス
永井豪とダイナミックプロ原作の『鋼鉄ジーグ』(1975年)では、磁石による球体関節の可動を取り入れた玩具がタカラから発売されヒット。『ガ・キーン』は、それを受けての作品でした。放映スタートの1976年は、ロボットアニメが急激に増加した年。放映された巨大ロボット作品は『UFOロボ グレンダイザー』『UFO戦士 ダイアポロン』『大空魔竜ガイキング』『ゴワッパー5 ゴーダム』『超電磁ロボ コン・バトラーV』『グロイザーX』『ブロッカー軍団Ⅳ マシーンブラスター』という具合で、まさに戦国時代、商戦のピークという時期でした。
その中で、『ガ・キーン』は単にメカ要素が多いだけではなく、ひときわシャープでソフィスティケイトされたセンスを見せつけてくれた作品でもありました。ロボットデザインひとつ取っても、流麗なラインが実に美しい。全身フォルムは腰の部分を略すという大胆な構成、さらに高次曲線が人間の鍛えた身体が持つ美しさを連想させ、特に筋肉を連想させる逆三角形の上半身、肘から先や膝から下のふくらはぎのくびれた感じは、まさに「人型の美学」です。
まだ他のロボットが円柱、角柱で手足を構成していた時代、こんな洗練された作品づくりが可能となったのは、東映動画(現:東映アニメ)がロボットアニメのノウハウを注ぎ込んだオリジナル企画として立ち上げたことと無縁ではないと思います。ガ・キーンというネーミングひとつとっても、効果音と一致する(第1話のサブタイトルの読みは“ガッキーン!”という効果音で実現されている)他に、“Gathering Keen”(集合して強くなる)という裏設定が考えられ、力の入れようがわかります。
原作のクレジットは「東映動画プロジェクトチーム」。原案構成の浦川忍は同社の横山賢二プロデューサーのペンネーム、キャラクターは『ゲッターロボ』『グレンダイザー』等を手がけてきたオープロダクションの故・小松原一男、メカデザインと美術は東映動画の辻忠直という布陣で、玩具メーカーや専任デザイナーの作品ではなく、アニメ専任者発なことも、一種の純度の高さのもとになっているのでしょう。
世の中には「ジャンル・ムービー」という考え方があります。スパイものとか、戦争映画とか、そういうもので、そこには必ず頂点を極めた「マスターピース」なる職人芸の絶品があります。ロボットアニメもひとつのジャンル・ムービーだとすると、この『ガ・キーン』第1話、そこで描かれた「濃密さ」こそは、必見のマスターピースと言えるものなのです。
【2003年1月27日脱稿】初出:「月刊アニメージュ」(徳間書店)