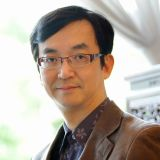●怪獣に生命を与える電気の光、それは科学の象徴か?
先日、ある雑誌にウルトラシリーズDVDのレビューを書いた。「高画質で嬉しいことのひとつは、セブンや怪獣の電飾が美しく見えるようになったことだ」という趣意である。すると編集者からは「光ってるのは当たり前だと思ってましたが、そう言われると美しく見えてくるんですよね」と感心されたのだった。当然と思っているようなことでも、こうやってひとつずつちゃんと言語化する大事さを、そのとき改めて実感した。
ウルトラ怪獣やヒーローに仕掛けられた小さな電球。思い出せばその光は、自分の人生に影響を与えるほど大きな魅力を放っていたものなのである。
一番最初に私が怪獣にハマったのは映画ではなく、テレビ特撮『ウルトラQ』の岩石怪獣ゴルゴスだった。放映スタート当初は「怪談仕立て」だと思いこみ、怪獣とは妖怪のように人の心胆を寒からしめる「怖いもの」と思いこんでいた。少年マガジンの石原豪人らの怪獣イラストも、おどろおどろしいタッチで恐怖の存在として描かれ、目をそむけるしかなかった。
だが、自分の目でフィルムを確かめてみると、怪獣とはエネルギッシュに動きまくる驚きの生命体なので仰天してしまった。飛び出した岩が集まり、再生して生き物の形をとる。背中は岩盤で硬く腹は妙に柔らかく、表情は強そうで笑っているような不敵さをたたえ……と、怪獣はいろんな要素が固まって空想の力を刺激する生き物としてフィルム上では描かれ、パワフルに活動している。そこから怪獣にのめりこむ人生が始まってしまった。
ゴルゴスの特徴の中でもひときわ強く興味をひいたのが、ギラギラと光る三白眼と、そして岩を集める中心──収縮とともに不気味に明滅する心臓部分である。そのどちらもが、電気の力で光ることで、強い印象を残した。以来、怪獣と言えば私にとってはまず「眼や身体の一部が電飾(機電)で光っていること」が大事な条件である。ラゴン、ペギラ、パゴスもその眼光に強い印象が残っており、スチル写真でも眼が点灯していないだけで何だか別の生き物に感じてしまうほどだった。
『ウルトラQ』も放映が進むと、単に眼が光るだけではない超常の生き物が現れる。それはケムール人である。眼そのものに左右にゆれ動くというアクションが取り入れられたこと、そして複数の電球を顔に仕込んで明滅させることで表情を出した倉方茂雄氏による機電の功績は大きい。
この「流れるような光」は、ネロンガの角やメフィラス星人の口、ゼットンの顔にも受け継がれ、超兵器マルス133にも使っていることもあって、科学的ですらある印象を彩りとして加えたように記憶している。
この時代、電気で流れる光は小中学生にとってどれくらい魅力的だったのだろうか。それは放映数年後の1970年ごろに自転車に方向指示器(フラッシャー)を付けるブームが起きたことからも、容易に思い起こせる。メーカーがいろんな方式で右折、左折のための電飾を自転車につけて競い合ったのである。そして通学に自転車を使っていた中学生にとっては、その電飾の手の込み具合が、変速器とともに重要なことになった。
単なる電球が左右に装着され、明滅する「ウインカー」ではもちろん不充分。「フラッシャー」と呼ばれるユニットが荷台の下に置かれたものの方が上等だ。さらに、その中でも1個の電球が回転板とモーターで流れるのは手抜きとわかるからこれもダメ。ちゃんと5~6個の電球が用意され、電子回路による制御で光が流れていくのが一番偉いというヒエラルキーがあったわけだ。
こうして順次明滅する制御回路について興味をもち、「ラジオの製作」などの雑誌に載っていた回路例を見よう見まねで、中学・高校と秋葉原で部品を買って自作してみりしたのが、自分の電気への興味の始まりだった。その経験が、やがて自分の進学・就職(電機メーカー)へと大きな影響を与えていく。その原点にも、怪獣の機電があったということになる。
いまやビデオデッキやステレオ、自家用車の電装品がずっと当たり前になって久しい。この「流れる光のありがたみ」も、世代的にはすっかり判らなくなったことだと思う。だが、怪獣や自転車の方向指示器の光の明滅に「科学」を感じてしまったのは事実だ。それは高度成長時代、ギラギラと明滅していたネオンサインと同じく時代の象徴だったのかもしれない。
そもそもゴジラの眼には電飾は入っていない。では、誰がいつどういう理由で怪獣の眼に電飾を入れ始めたのだろうか。ウルトラマンの眼には電飾が入っている。ということは、人間らしいヒーローというよりは怪獣らしさの象徴が眼の光に集約されるのではないか……等々、電飾に関する疑問と興味は、いくらでもわいてくる。「アニメ特撮における光とは何か」は、一大研究テーマでもある。
造形的な資料や研究にしても、電飾に関するものはウルトラシリーズの機電を担当した倉方茂雄氏によるメイキング写真が少し出ているくらいで、どんな回路や仕掛けを使ってどういう効果を挙げたのか、わからないことの方が多い(編注:その後、映像で紹介されたものが多数リリースされた)。
ということで、怪獣映画でも「わかっているようでわかっていないこと」が残っている。そのひとつに「電飾」というアイテムがあると思う。掘り尽くしたようにも思われている怪獣映画の鉱脈、まだまだ研究テーマは残っているのではないか。
【2002年5月7日脱稿】初出:「宇宙船」(朝日ソノラマ)