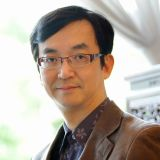※2002年9月10日発売号の原稿です。
《前説》
来たる2003年は、(『鉄腕アトム』から数えて)TVアニメ40周年にしてビデオアニメ20周年という年です。歴史は繰り返すと言いますが、その単位が20年=ワンジェネレーションだとすると、一周目にビデオアニメが誕生して、二周目が来年という構図になるわけで。興味深いポイントです。確かに双方向TVだの映像配信だの、次なるメディアの変革は来ていますね。ベータマックスも終息したしなあ……。
●懐かしき80年代テイスト
今年、あるアニメ映画を見ていたときに、妙に懐かしい気持ちになって不思議に思ったことがあります。ツッコミどころ満載の作品ゆえ、ここでは名前は挙げませんが、その懐かしさとは「そういや80年代には、こんな練れていないビデオアニメを死ぬほどたくさん観たなあ……」という記憶から生じたものでした。
オリジナル・ビデオ・アニメ(OVA)は、かつてAV機器の普及時期やバブル期に勃興し、時代の役目を担って量産されたものでした。趣味性の高い企画があまり揉まれずに成立するようなところがあって、非常にわかりにくい作品や、凡庸で早く終わらないかと時計を見たりする作品も少なくありませんでした。
DVD時代になって、年月を経て印象の変わるもの、今観ることに新しい価値の発見できるものも続々リリースされているので、それは良いことですね。
──と長い前置きで、今回は『ドラゴンズ ヘブン』というOVAの話です(編注:当時8月下旬に3800円の廉価版DVDが発売)。
アニメは基本的に総合芸術で、映画と同じように主題や物語があって、それを観客が体感することで成立しているものです。だから見終わった後で「面白い面白くない」と語るときには、主としてストーリーのことを話すと思います。そのような観点からすると、今回取り上げるこの『ドラゴンズ ヘブン』、OVAにありがちだった歪みを持った作品です。でも、「いいじゃん、好きで買っちゃったんだし……」というのが、今回こだわってみたくなった動機です。
●千年を超える機械生命体との戦い
物語は、吹きあげる砂塵の中からスタート。巨大な戦闘機や空中戦艦、戦車やロボットのようなものが壮絶な戦闘を繰り広げる遠未来の戦争シーンから始まります。人間と機械生命との戦いは、殲滅作戦の実行により終局を迎え、思考能力を持った戦闘ロボット“シャイアン”はオペレータの人間を失って空母の残骸の中で永い眠りにつきました。やがて近くを通りかかった少女イクールの生体反応に呼応して目覚めたシャイアンは、一千年の時が流れていたことを知り、物語はここにいたってもまだ続いてる戦争の中で、シャイアン最大のライバルだった機械生命体“エルメダイン”との決着を描いていきます……。
製作は1988年で、監督は同名のコミックを発表した原作者・小林誠。主としてメビウスに代表されるようなフランスやアメリカのコミックに大きな影響を受けた作品で、イラスト感覚がそのまんま飛び出てきたような作風です。小林誠はモデラーとしても辣腕で、アバンタイトルは自身のモデルを使った実写パート。小林誠はメカデザイナーとしてもアニメに参加、『機動戦士Zガンダム』のモビルスーツ“ジ・オ”、“バウンド・ドック”や、続編のZZガンダムの基本デザインなどを提供していまして、この作品のメカからもその体臭は存分に立ち上ってきます。
つまりこれは、イラストレーターで漫画家でメカデザイナーでモデラーでもある、マルチ・クリエイター小林誠ワンマンショーのような作品です。そこで描かれるものは、妙な存在感を持った巨大メカニズムであり、パイプ類が複雑に入り組んだような背景であり、細かい点をタッチのように描きこんでディテールアップされた世界で、好きな人にはたまらないものだと思います。
とはいえファンでもないし、そういったものにあまり興味ない私が、なぜこの埋もれた作品に惹かれるものを感じるか──作品の妙なテイストに引っかかるのはもちろんですが、そのテイストとは何か、なぜ引っかかるのかなのですね、本当の問題は。
●突出したところの多い先鋭的な作品
まず再見して思ったのは、いろんな意味で突出した作品だったんだなあ、ということです。
最初の画面はビデオ撮影による実写映像からスタート。小林監督自身による近い巨大な主人公シャイアンのフルスクラッチ像が、スモークをたいた中に浮かび上がり、歩き出します。サポートする造形作家も竹谷隆之と韮沢靖──昨今のフィギュアブームの立役者だったりして、その辺も時間が経ったからこその味わいの一部です。造形物の出来映えも並々ならぬ素晴らしさがわかるもの。ところが、ビデオ撮影のために動かすと逆に小さいもののように見えてしまったりして、好意的に解釈すれば、そういった失敗を恐れないところが、突出感を強くしているのでしょうか。
続くオープニングアニメーションのブロックは、メカ作画では実力のある山下将仁の担当。メカの重みが感じられ、絶妙な臨場感をともなった作画が展開します。被弾した戦闘機が、空中で爆発時に回転してひねりを加えながら四散したり、砂煙を上げて接近するメカが微妙なリズムをともなって、ぬめるような動きを見せるのが、異様でかつ面白い部分です。実際、私自身このパートが観たくて買ったようなものです。
改めて見るとスタッフも豪華で、キャラクターデザイン(イクールのみ)は平野俊弘(現:俊貴)、作画監督は斎藤格、メカ作監督は大平晋也で、ナニゲに線画背景に高山文彦なんて名前が出るのもクレジットの見逃せないところ。
集中豪華主義的なところは、キャストにも現れています。メインキャストは3人しかいないのですが、主人公シャイアンは家弓家正。冒頭の雄大な戦闘シーンのナレーションは独特の重みを持った重々しいナレーションで語られているのですが、場面転換すると「千年も経っちゃったんだな、これが」と、明るいセリフが流れるので、思わず仰天(笑)。家弓家正と言えば、非常に重みと威厳と格式を備えている偉大なベテラン声優の一人であるわけですが、そのイメージとちょっと似つかわしくないような役を振って違和感出すということかも。これにイクールの皆口裕子とエルメダインの富山敬という取り合わせ。いずれもどことなく、ものにこだわらない大らかさを感じるところが、いい味出した演技をしています。
●今になってわかる新鮮さの所在
全体の映像は、昨今のアニメを見慣れた目からすると、これがやけに新鮮で、それも今回の収穫でした。特に日差しの強い砂漠のぱきっと抜けたような色味は、DVDの色ノイズの少ない画面に合っていて、豪快でいい感じです。
メカ描写も、影やハイライトがほとんどなく、塗り分けすらなくて単色なのが、これまた清々しい。その分、ディテールに凝っていて、凹凸の激しく、立体面の組み合わせの複雑なメカをよく動かしていますし、セル画の1枚1枚に点を無数に描きたして独特の雰囲気を出しています。
一方、ここに掲載した写真から想像されるイメージが、ひとつのストーリーにまとまって、まともな感動を覚えるような構成になってるか、そういう期待に応えるかというと、実のところ全くそのようなことはありません。物語は、わざとはずしたようなものばかり。意識を持った主役メカが可愛い女の子と出会ってともに戦うという以上のものでもないし、そこにも別に機械対人間の越境的な愛の葛藤があるかというと、まったく何にもありません。二人の交流も、天津甘栗をプレゼントするだけです(笑)。そもそも主人公シャイアンと敵対する機械生命体の出自の本質的な区別がつきませんし、クライマックスになりそうなライバルとの決戦ですら実は──という感じで、ハリウッド的ドラマツルギーからすると盛り上がらないことおびただしいわけですね、これが。
記憶をたどれば、製作当時に観たときには、緻密な作画に代表される映像構築への努力に比する世界観の不統一さ、物語へのあまりの欲求の少なさが非常にアンバランスに感じられ、もったいないというか、いらだつというか、そんな感想を抱いたものです。ですが、このやたらと大ざっぱなところが今観ると、何だか「ああ、このユルい感じがとってもいいなあ」なんて思ったりするから、人間は勝手なものですね(笑)。
小林誠監督はこの作品で自分が興味のあることを、わき上がる衝動や欲望のおもむくままにイメージを重ね、思いっきり詰め込んでいったのでしょう。目立った部分は、全部バラバラのピークとして立ち上っていて、連続感や全体での固まり感には結びついていないわけですが、もともと映画としての完成度には興味がわかなかったんじゃないかと推察します。そういったものを目指してつくられた作品ではないのに、目指していない部分を出来ていないと評価するのは、一種の「ないものねだり」で、別の評価軸がいるのでしょう。
先述の欧米コミックの世界では、物語や世界観をユルくして、ここだ! というところのイラスト的精度を高くしたものはいくらでもあるわけで、だとするとそういうアニメもあって良いわけです。
メカが出て来たら設定が無ければならない、キャラが出て来たら性格が見えなければならない、お話を振ったら落とさなければならない、そういうアニメのつくり方と楽しみもあるかもしれないけど、大きくはみ出した作品もあって良いのではないかなー、と残暑でユルくなった思考力で、考えさせられました。
バブル期真っ盛りにつくられた余裕のOVA群──皆さんにはどんな味が感じられるでしょうか。
【2002年8月28日脱稿】初出:「月刊アニメージュ」(徳間書店)